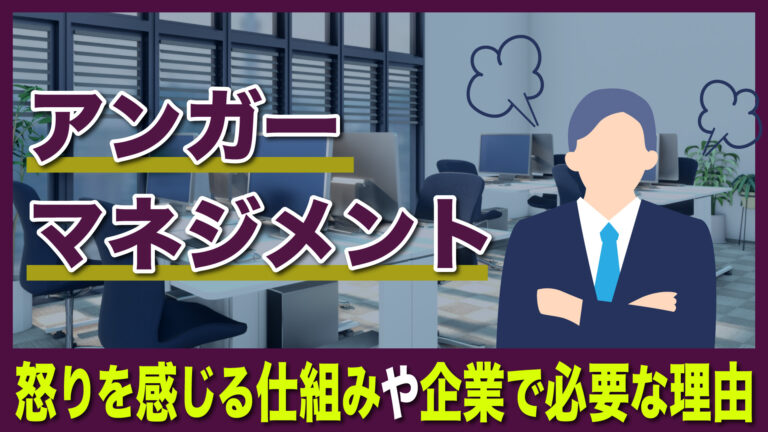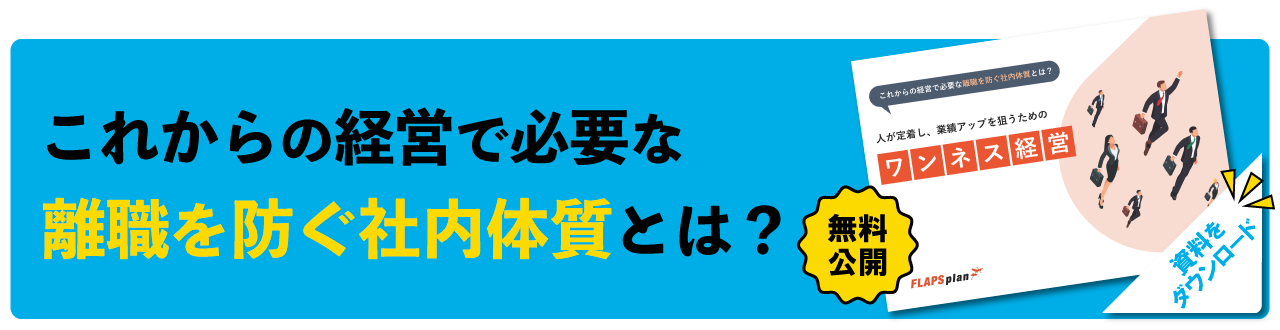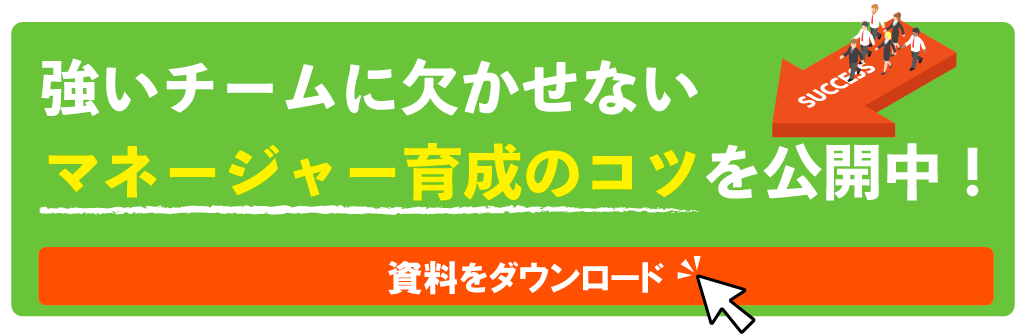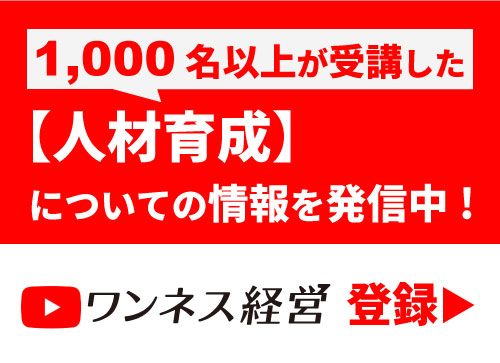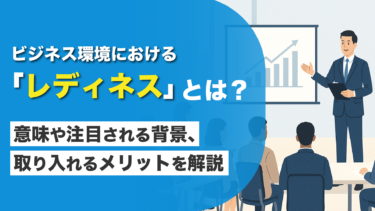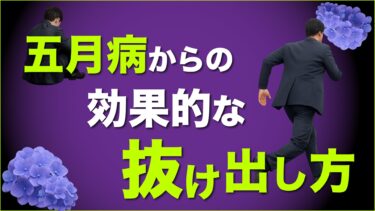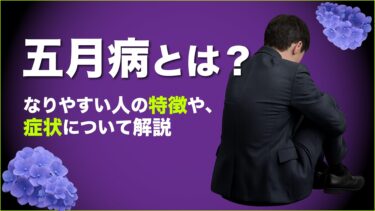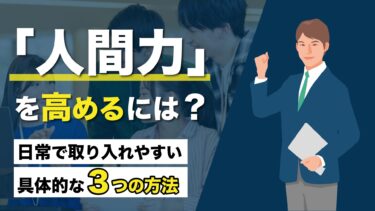「アンガーマネジメント」は、怒りの感情を適切にコントロールするためのスキルです。
個人はもちろん、企業にとっても役立つスキルであることから、「アンガーマネジメントについて理解したい」「社内に周知し、自社の人間関係をより良くしたい」という方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、アンガーマネジメントの概要を解説し、怒りを感じる仕組みやアンガーマネジメントが企業で必要な理由について紹介します。
アンガーマネジメントについて知りたい担当の方は、ぜひ参考にしてみてください。
アンガーマネジメントの概要
アンガーマネジメントは、私たちの日常生活で生じる怒りやイライラの感情を適切に管理し、コントロールするための実践的なスキルです。
単に怒りを抑え込むのではなく、健全な形で対処し、建設的な行動につなげることがアンガーマネジメントの目的です。
適切なアンガーマネジメントができないと、問題の責任を他者に転嫁したり、物に当たったりするなど、非生産的な行動につながりがちです。
また、時には自己否定的になり、自分を責めることで精神的な負担を増やしてしまうこともあります。
このような不適切に表れた怒りは、職場の人間関係を損なうだけでなく、業務効率や生産性の低下という形で組織全体にも影響を及ぼしがちです。
そのため、アンガーマネジメントは単なる個人的なスキルを超えて、職場の円滑なコミュニケーションと生産性を支える重要な要素として認識されています。
怒りを感じる仕組み
人が感じる「怒り」は、複雑な感情の仕組みから生まれます。
怒りの根底には、不安や恐れ、悲しみ、寂しさといった「第一次感情」が隠れています。
これらの感情は誰もが日常的に抱くものですが、「第二次感情」である怒りとなって表面化しがちです。
怒りは単独で存在するものではなく、常に第一次感情と結びついています。
つまり、内面に抱える不安や悲しみが大きければ大きいほど、表に出る怒りも強くなる傾向があるといえます。
特に注意が必要なのは、激しい怒りや長く続く怒り、頻繁な怒り、攻撃的な怒りです。
怒り自体は自然な感情ですが、その表れ方によっては周囲の人々や自分自身を傷つける原因となることがあるため、適切な対処が必要となります。
アンガーマネジメントが企業で必要な理由
企業でアンガーマネジメントが必要な理由は、下記の3つです。
- 職場環境の改善
- 良好な人間関係の構築
- 意思決定と業務効率の向上
それぞれ解説します。
職場環境の改善
職場での怒りのコントロールは、快適な環境づくりの基本です。
アンガーマネジメントを実践することでギスギスした雰囲気を防ぎ、社員の定着率を高められます。
また、怒りによるストレスが原因で起こる胃潰瘍やメンタル疾患のリスクを低減し、健康的な職場づくりにつながります。
良好な人間関係の構築
良好な人間関係の構築にも、アンガーマネジメントは欠かせません。
特に上司と部下の関係改善に重要な役割を果たすのが、アンガーマネジメントです。
怒りをコントロールできる上司は部下から信頼され、良好な人間関係を築きやすくなります。
職場全体のコミュニケーションの質が向上するのはもちろん、ハラスメント防止にも効果的です。
意思決定と業務効率の向上
怒りをコントロールすることで冷静で的確な判断が可能になり、理性的に働けるようになります。
また、感情的な行動による時間の無駄が減るため、業務の効率化が図れる点もメリットです。
アンガーマネジメントは、企業の成長に不可欠となる、新規事業の展開や業務改革などの実現にもつながりやすいといえます。
まとめ
アンガーマネジメントは、現代のビジネス環境において欠かすことのできない重要なスキルです。
怒りの感情が適切にコントロールされないと、個人だけでなく職場の人間関係や業務効率などにも影響を及ぼします。
怒りの感情は誰でも起こるものですが、それを適切に管理し、建設的な方向に導くことが重要です。
ぜひ、今回の記事を参考に、アンガーマネジメントについて理解を深めておくことをおすすめします。