Column
2022.01.25
リーダー必読!「褒めて伸ばす」の落とし穴
チームづくり

「わたし、褒められて伸びるタイプなんです」
ってよく聞きますよね。
逆に聞きたいんですが、叱られて伸びるタイプっているんでしょうか?笑。
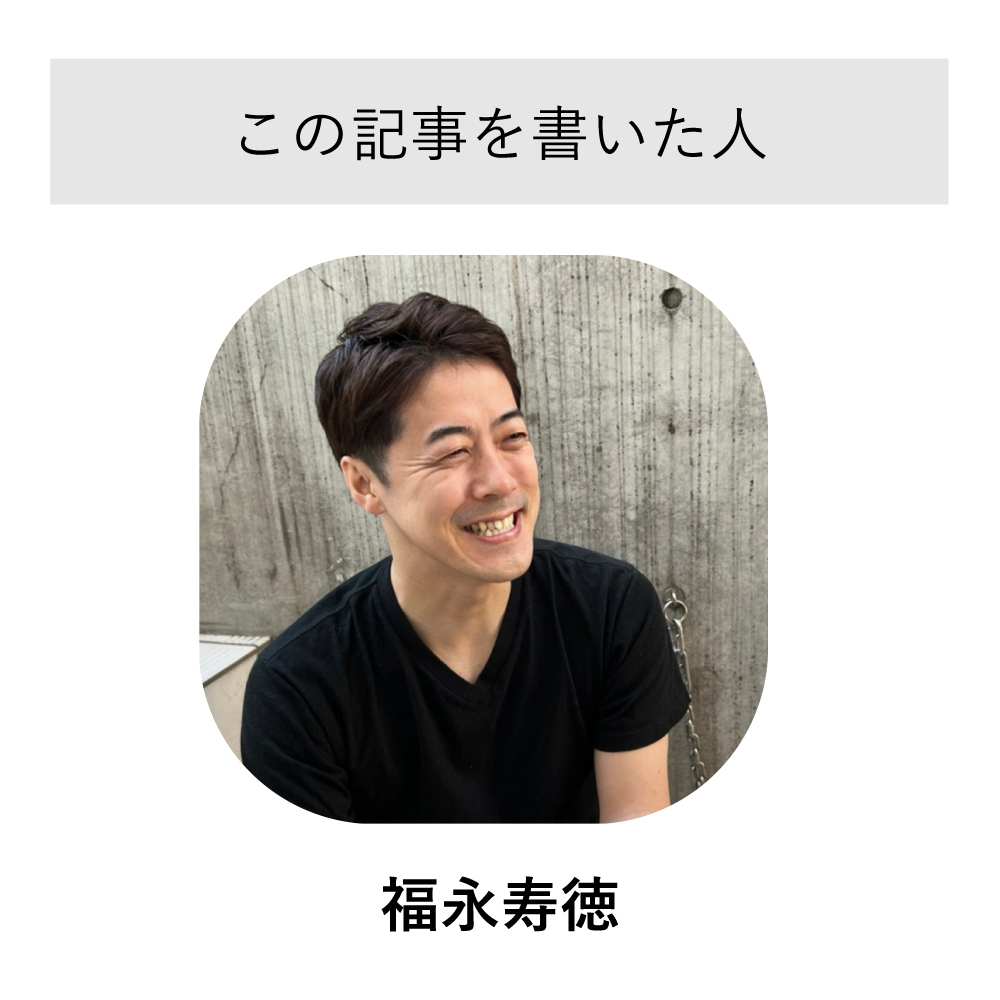
大学卒業後、ヘルスケア業界で1000名以上のトレーナーを育成。 セールス下手でも日本の隅々にまで展開することに成功。 好きで得意なことで役に立つと自分も周りも幸せだ。と確信する。 その後、独立起業。インナーブランディングの専門家として活動中。 趣味はトライアスロンだが走るのは嫌い。サウナとバスケ観戦が好き。 焼肉の部位はハラミ。フラップスプランの代表。
とりあえず、褒めて伸びるタイプですって先に言っておきたいのは、ミスっても叱らないで欲しいというただの防御策でしかないことをまずはご理解ください。
それでも、なお「褒めて伸ばす」
というのはなんとも甘美な響きであり、人材育成の理想郷な感じがします。
ところが「褒める」のが苦手という人も結構います。
褒めるのが苦手という人は大体どっちか。
- 自分の基準が高すぎて何をみても大したことないと思ってしまう
- 自分なんかに褒められても嬉しくないんじゃないかと思ってしまう
両方ボリューム調整せえよ。と思います。笑。
大したことないって言ってマウントとって何が都合がいいんでしょうか。
自分なんかに、って小さく見せて何が都合がいいんでしょうか。
褒めるというのは心の報酬です。
その効果をしっかり理解して褒めていきたいですね。
ただ!褒めるってのはなかなかの諸刃の剣です。
リーダーが知っておくべき「褒める」の落とし穴についてまとめました。
「褒める」と「承認する」の違い

早速ですがひとつ質問です。
「褒める」と「承認する」の違いって説明できますか??
「褒める」とは、
人のしたこと、行いを優れていると【評価】してそのことを言う。たたえること。
「承認する」とは、
そこにある事実を【認める】こと。
この違い。わかりますか?
「褒める」には【評価】が入っていて
「承認する」は【事実を認めて伝える】だけ
というのがポイントです。
人は誰からどんな風に褒められたい?

実は「褒める」というのは難易度が高いことなんです。
一歩間違えると、相手をねぎらって距離を縮めるつもりで言った言葉が、逆効果になってしまいます。
それは
人は【評価されたいと思う人から評価されたい】
という思いがあるからです。
尊敬している人とそうでもない人、どっちから褒められると嬉しいか。
もちろん、そうでもない人から褒められてもまあ、悪い気はしないんですが、やはり自分が尊敬していたり、自分のことをよく理解している人から褒められると嬉しいわけです。
同じ「褒める」にしても【誰が言うか】によって全然感じ方が変わってしまうのです。
どうですか?
あなたはスタッフから「褒められて嬉しい人」になれているでしょうか?
って聞かれるとドキッとしません?
褒める時は本音が大事
もう1つ褒めるときの落とし穴をご紹介します。
それは
本当にそう思っていないと嘘っぽくなる
ということです。
当たり前なんですけどね。
いわゆる「お世辞」ですね。
急に社員から
「社長、最近、吉沢亮に似てきましたね」
って半笑いで言われて
「えー!ほんとに?やっぱ最近ジム行き始めたからかなぁ」ってならんでしょ。
(いや、たまに本当にそう思う人がいるから経営者ってすごい。逆に。)
平均80点のテストで60点だった子に対して
「60点すごいじゃん!」
って言ってもなかなか届かない。
あ
まとめ
褒めるの落とし穴についてまとめてみました。
なんでも褒めればいいってもんじゃないんです。
- 褒められて嬉しい人になること
- 本音で伝えること
これを大事にしていきましょう。
今日はがんばったね。
じゃなくて、
今日もがんばったね。
です。
「は」と「も」で、かなり印象違います。
リーダーは言葉を磨いていきましょう。
生産性を向上させるコミュニケーション
チームリーダーと一般メンバーでは立場や経験の違いから、コミュニケーションがすれ違ってしまうことがあります。
すれ違いをなくすためには、伝える側と受け取る側の双方がそれぞれどのようなことを注意するべきなのか?ポイントを知りましょう。
円滑なコミュニケーションを行い生産性を向上させるヒントを公式LINEにて配信中です。今日からすぐに実践できるコミュニケーションのコツを知りたい方は下のボタンからLINEを追加し配信を受け取ってください!
事務局:スズキヒラク


この記事を書いた人
![]()
福永寿徳
大学卒業後、ヘルスケア業界で1000名以上のトレーナーを育成。 セールス下手でも日本の隅々にまで展開することに成功。 好きで得意なことで役に立つと自分も周りも幸せだ。と確信する。 その後、独立起業。インナーブランディングの専門家として活動中。 趣味はトライアスロンだが走るのは嫌い。サウナとバスケ観戦が好き。 焼肉の部位はハラミ。フラップスプランの代表。
関連記事
-

2023.02.07
社内研修制度を導入するメリットとは?必要性や注意点も解説
チームづくり社員の育成は企業の成長のために欠かせないものです。 そのため、多くの企業では社内研修制度を取り入れて人材育成に努めています。 これから自社に研修制度の導入を検討する場合、「どんなメリットがあるのか」「なぜ必要なのか」といった疑問を持つ方も多いかもしれません。 そこで今回の記事では、社内研修制度の導入によって得られるメリットや必要性、注意点などを解説し、社外に依頼するケースについても紹介していきます。 研修制度の必要性・目的 研修は、勉強会や各種講座などに参加し、業務に必要となる知識やスキルを習得することです。 基本的なビジネスマナーを学ぶ研修や特定の業務に関わる研修、リーダーになる人のための研修など、現場での仕事では学べないさまざまな種類のものがあり、優秀な人材を育成するために欠かせないものとなっています。 また、社員一人ひとりの評価や働き方、キャリアプランの実現にもつながっていくことから、企業にも社員にも必要性の高い制度だと言えます。 研修制度の目的として挙げられるのは主に下記の2つです。 組織力の向上 学びの環境の整備 それぞれ解説します。 組織力の向上 研修制度の最も大きな目的として、組織力の向上が挙げられます。 近年の市場環境やIT技術の進化に伴い、企業を取り巻く環境も大きく変化しています。 企業が強い組織になって競争に勝ち抜くには、スキルやノウハウの陳腐化を防ぎ、生産性をアップしなければいけません。 そのため、研修制度による情報や知識などのアップデートが必要不可欠です。 また、社員の学びをサポートする研修制度は普段の業務パフォーマンスを高めることから、企業の業績向上にもつながります。 学びの環境の整備 知識やスキルが学べる環境を整えることも目的の一つです。 多くの企業では、研修として実務を通した「OJT」を取り入れていますが、その内容は実際の担当業務に限定したものになりがちです。 研修制度を導入することで、知識・スキルの体系的な習得が可能になり、OJTの内容が補完できます。 加えて、業務全体の理解度も深められ、トラブルや緊急時の対応がスムーズになります。 研修制度の導入メリット それでは、研修制度を導入することにどのようなメリットがあるのでしょうか。 研修制度を導入するメリットとして、次の3つがあります。 社員のスキルアップ 社内風土の改善 社外への効果的なアピール それぞれ解説していきます。 社員のスキルアップ 研修制度を取り入れることで、社員のスキルや知識が向上します。 研修に参加した社員は、学習内容を自分の業務においてアウトプットすることで、さらに理解が深まり効果が上がりやすいはずです。 また、自費で研修に参加する場合、金額を負担しなくてはいけませんが、自社に研修制度が導入されていれば安心して参加できます。 そのため、レベルの高い研修に挑戦しようといった学習意欲の向上につながりやすい点もメリットになります。 社内風土の改善 社内でこれまでに培われた風土や雰囲気は、変化や改善が必要となるケースもあります。 こういった場合、研修制度を導入すれば改善が可能です。 例えば、マネジメント研修を行うことで、管理職にステップアップするという意識が高まったり、行動が積極的になったりして、社内の雰囲気が変化するはずです。 また、人材育成を行うという風土ができれば、社員が自主的にスキルの向上に取り組むことにもつながります。 社外への効果的なアピール 研修制度を導入していることは企業としてアピールできる事項の一つです。 特に新卒採用の場合、基礎スキルが学べる研修制度が整っていないと不安を与えることになり、中途採用の場合でも研修でキャリアアップを支援してもらえるかを重要視しています。 研修制度が導入されているかどうかは就職活動において参考にされることが多く、優秀な人材採用のためにも欠かせないものです。 よって、研修制度は人材育成の面だけでなく、採用の面においてもメリットになると言えます。 研修制度を導入する際の注意点 社内研修制度を導入する際には、注意点もあります。 まず、いきなり全社的に導入すると社内が混乱する可能性があるため、注意が必要です。 一部のポジションや部門に絞り、小規模にスタートしてから全社に展開していくスタイルが好ましいと言えます。 また、研修制度の効果を高めるには改善を繰り返すことが重要であり、その際に大切なのは実際に研修制度を利用した社員からのフィードバックです。 必ず受講者全員からフィードバックをもらい、効果を検証して方法や内容の改善を行っていくと良いです。 社外に依頼する場合 研修制度は社内だけで行うものと決まっているわけではありません。 場合によっては社外に依頼するケースもあります。 その際は、研修の準備にどれくらいの時間と費用をかけられるかどうかで検討することがおすすめです。 例えば、新入社員向けのビジネスマナーや社内コミュニケーションの活性化、マネジメント研修などは、講習のプロや専門家に依頼することでスムーズに理解が進みます。 一方、自社に関する内容の研修が必要な場合は、社内の人が研修を行ったほうが良いと言えます。 まとめ 人材育成には欠かせない社内研修制度ですが、その目的として組織力の向上や学びの場の整備などが挙げられます。 社内研修にはスキルの向上や社内風土の改善といったさまざまなメリットがあり、社外へのアピール効果も大きいです。 また、ニーズに合わせて社外に依頼するという方法もあります。 ぜひ、今回の記事を参考にして、社外への依頼も含めた社内研修制度の導入を検討してみてください。
-

2022.11.29
アダプティブラーニング|企業の導入事例を紹介!
チームづくり一人ひとりに合わせた学習が可能なアダプティブラーニングは、教育機関のみならず、企業の人材育成にも大きく役立ちます。 導入を検討している場合、「自社に取り入れたらどのように活用できるのか」「導入している企業の具体例を知りたい」と思っている方も多いのではないでしょうか。 今回は、前回お伝えしたアダプティブラーニングの企業向けサービス・ツールの中でも、「Cerego」「Core Learn」を導入している企業の事例をご紹介します。 アダプティブラーニングのおさらい アダプティブラーニングは、さまざまなIT技術を利用しながら学習者それぞれの理解度や進行度に合わせて行う学習方法を指し、「適応学習」とも言われます。 文部科学省が「すぐにでも着手すべき課題」としているように、国内の教育現場において推進されているのが、このアダプティブラーニングです。 そして、学習者一人ひとりに合わせた学習のやり方は、教育現場のみならず企業の人材育成にも大きな効果があるとされています。 現在、すでに多くの企業でeラーニングが取り入れられていますが、双方向でのコミュニケーションが可能なアダプティブラーニングは、さらに多様化した学習方法だと言えます。 西日本旅客鉄道株式会社の事例 代表的な企業向けアダプティブラーニングの一つとして、Ceregoがあります。 Ceregoは、記憶定着に特化した学習システムで、何度も繰り返し復習問題を解きながら知識を定着していく点が特徴です。 北陸や近畿地方、中国地方といった西日本を中心に鉄道を運営する「西日本旅客鉄道株式会社」(JR西日本)では、Ceregoを導入し、運輸関係司令職員の知識習得に役立てています。 運輸関係司令職員が行う業務には、ダイヤ乱れ解消などさまざまなものがあり、マニュアルや業務内容の把握をはじめ、多岐にわたる知識が必要です。 以前より、JR西日本では運転マニュアルなどをペーパーレス化する取り組みを実施しており、運輸関係司令職員はタブレット端末を利用しながら業務を行っていました。 その上で、情報発信や知識共有のさらなる効率化が検討され、導入が決定したということです。 また、隙間時間を有効活用して学べるように設計されたシステムは、多忙な運輸関係司令職員にとって最適だと言えます。 導入の結果、職員一人ひとりの学習意識が高まったことや、情報伝達やアップデートのスピード化といった成果が出ています。 株式会社三菱UFJ銀行の事例 印刷会社大手の凸版印刷が提供しているCore Learnは、企業向けの完全習得型学習管理システムです。 当初から金融機関に向けたeラーニングに特化していることもあり、3大メガバンクの一つ「株式会社三菱UFJ銀行」でも導入されています。 銀行の社員は、業務に必要となる、お金に関するさまざまな知識を完全に習得しておかなければいけません。 三菱UFJ銀行では、2016年から、新入社員の金融知識習得のためにCore Learnを取り入れました。 Core Learnには「法務」「税務」「財務」「為替」の4つのコンテンツがあります。 三菱UFJ銀行ではこれらをベースに、自社に特化した内容を盛り込んだ「骨太ドリル」を作って導入しています。 自社独自の教材を活用することで学習者の理解度も向上し、社内テストでは前年比より16%も全体の点数が上がったそうです。 また、理解度だけでなく、わからない部分を教え合ったり知識を共有したりといったチームワークにも効果がありました。 まとめ これまで教育機関向けのものがほとんどだったアダプティブラーニングですが、企業でも活用が進んできています。 導入する際は、自社の人材に関する課題を明確にした上で、適切な学習システムを選択することをおすすめします。 ぜひ、今回の企業事例を参考にアダプティブラーニングの導入を検討し、人材育成に活用していきましょう。 [sitecard subtitle=関連記事 url=https://flapsplan.co.jp/blog0160/ target=] [sitecard subtitle=関連記事 url=https://flapsplan.co.jp/blog0162/ target=]
-

2024.11.19
人材定着のためのポイントとは?具体的な施策も紹介
チームづくり企業の持続的な成長において、人材定着は重要な課題の一つです。 安定した人材基盤は、業務の生産性と効率性を高めるだけでなく、組織全体の専門性向上にも大きく貢献します。 人材定着の重要性を認識しながらも、どのようにすればいいのかわからないという方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、人材定着のポイントや具体的な施策について紹介します。 ぜひ参考にしてみてください。 人材定着のためのポイント 人材定着のためには、次の2つのポイントを押さえておく必要があります。 入社後のミスマッチを防ぐ情報開示 相談・コミュニケーション体制の確立 それぞれ解説します。 入社後のミスマッチを防ぐ情報開示 人材定着の第一歩は、採用段階での適切な情報共有です。 配属先や業務内容について、実現可能な将来のキャリアパスを含め、ありのままの企業の姿を伝えることが重要です。 求職者のニーズに寄り添いながらも事実に基づいた情報を提供すれば、入社後のギャップを最小限に抑えられ、新入社員の定着率向上につながります。 相談・コミュニケーション体制の確立 「相談しやすい環境」は成長できる企業の特徴として重視されています。 部署を越えた横断的なコミュニケーション環境を整備することで、業務上の問題解決がしやすくなるだけでなく、仕事以外の人間関係も構築可能です。 このような適切な環境が従業員の帰属意識を高め、長期的な定着につながります。 人材定着のための具体的な施策 人材定着のための具体的な施策として挙げられるのは、次の3つです。 働く環境を改善する 従業員同士のつながりを作る キャリアアップをサポートする それぞれ解説します。 働く環境を改善する 育児・介護休暇、時短勤務、テレワークなど、従業員のライフステージに応じた柔軟な働き方に対応するには、個々の事情に配慮した働き方改革を進める必要があります。 業務過多や人間関係の課題を抱える従業員に向けて環境を改善することで、やむを得ない離職を防げます。 たとえば、残業時間の削減や年間休日の適正化に加え、完全週休2日制の導入や相談窓口の設置などがおすすめです。 ただし、労務環境の悪化には必ず根本的な原因が存在するため、単なる制度の導入だけでは本質的な解決には至りません。 まずは自社の現状を正確に把握し、問題の本質を理解することが重要です。 その上で、根本的な課題解決に取り組みながら、必要な制度を段階的に導入していくアプローチが望ましいと考えられます。 さらに、従業員の離職防止には、公平で透明性の高い評価制度の確立が必要です。 360度評価や業績連動型のインセンティブ制度など、成果を多角的に評価できる仕組みにより、従業員の「正当に評価されていない」という不満を解消できます。 その際、評価基準を明確化して全従業員に周知することで、制度の実効性も高められます。 従業員同士のつながりを作る 人材定着には、部署を超えた従業員間の交流が重要な役割を果たします。 たとえば、異なる部署の従業員がランダムにペアを組んで昼食を一緒にとる「シャッフルランチ」は、自然な形で新しい出会いを生み出す効果的な取り組みです。 また、従業員が自由に集まり交流できるスペースを設置したり、「もくもく会」などの部署横断型の勉強会を開催したりすることで、業務の枠を超えた関係構築が促進されます。 さらに、部署内での良好な人間関係づくりも欠かせません。 定期的な1on1ミーティングの実施やメンター制度などの導入により、直接の業務関係がない上司や先輩・後輩、同僚との間でも信頼関係を築くことができます。 こうした重層的なコミュニケーション機会の創出が、働きやすい職場環境の実現につながります。 キャリアアップをサポートする 従業員のキャリア形成サポートは人材定着に役立ちます。 スキルアップを支援することで転職を促進してしまうのではないかという懸念があるかもしれません。 しかし、ジョブ型雇用や成果主義が主流となった今日では、むしろキャリア形成の機会が限られている企業ほど、従業員の離職リスクが高まる傾向にあります。 効果的なキャリアサポートには、業務に関連したセミナーへの参加促進や資格取得支援、定期的なキャリア面談の実施が含まれます。 また、充実した社内研修プログラムの提供、計画的なジョブローテーションの導入も有効です。 特に若手従業員は成長意欲が強く、このような学習機会の提供は、早期離職の防止に大きく貢献します。 まとめ 人材定着の実現には、入社前からの適切な情報開示や相談しやすい職場環境の整備などが重要となります。 また、具体的な施策として、働く環境の改善、従業員同士のつながりづくり、キャリアアップのサポートなど、包括的なアプローチが効果的です。 これらの取り組みを通じて、従業員一人ひとりが安心して成長できる職場を作ることができます。 まずは自社の現状を見つめ直し、できるところから着実に改善を進めていくことをおすすめします。
私が変わると、チームが変わる
ワンネス経営®プログラムは、インナーブランディング強化というアプローチを通して、 お客様企業が求める成果を達成していくという「新しいチームビルディングのプログラム」です。 イメージが持ちづらい点があるかもしれませんが、どうぞお気軽にご質問、ご相談ください。