Column
2023.01.19
戦略と戦術の違い
チームづくり

戦略と戦術。
ビジネスはよく戦争に例えられる。
しかし、それが話を複雑にしている気もする。
本当に例え話として的確だったからなのか?
それとも、一昔前の男性たちが仕事ってものをちょっとだけすごそうに見せて近寄り難いものにしたかったのか?は分からない。
今回は戦略と戦術ってそもそもなんだっけ?
という方に向けた記事です。
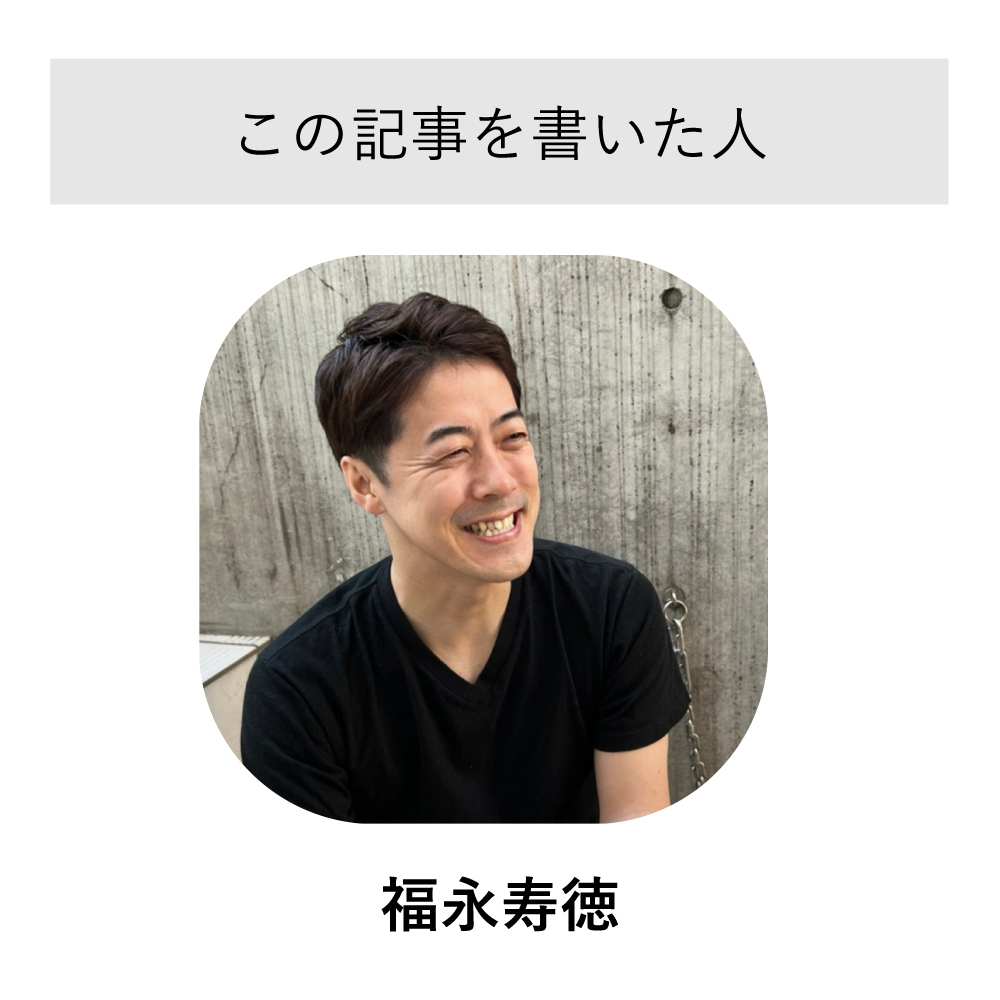
大学卒業後、ヘルスケア業界で1000名以上のトレーナーを育成。 セールス下手でも日本の隅々にまで展開することに成功。 好きで得意なことで役に立つと自分も周りも幸せだ。と確信する。 その後、独立起業。インナーブランディングの専門家として活動中。 趣味はトライアスロンだが走るのは嫌い。サウナとバスケ観戦が好き。 焼肉の部位はハラミ。フラップスプランの代表。
村一番の働き者
どうでもいいが、私の中には村一番の働き者だった遺伝子が入っている気がする。
家系図をさかのぼったわけでもなく、想像でしかない。
しかし、この身長180cm体重80kgという体格から鑑みるに、農耕生活だろうが狩猟生活だろうがきっと先祖のうちの誰かは村で一番の肉体労働力だった。と思える。

そんなことをちょっと想像してみた。
とある時代のとある稲作の村。
「おーい!ふくさんや!今日は何すんの?」
「おー、今日はあの杉の木の下まで耕して田んぼにするのよ」
大きな体で効率よく作業を進めるふくさんは村人のまとめ役だった。
「でも、なんで村長は杉の木の下までやれって言ったんだろうね?」
「さあ?分からない。でも村長から言われたからには杉の木の下まで早く丁寧に耕すだけだ」
ふくさんは力強く鍬(くわ)を振り下ろしながら返事をした。
「おれは『どうやって耕すか?』を考えるのは得意だけど、『いつまでにどこまで耕すか?』は苦手なんだよなあ〜」
気合いと筋力と機転と笑顔でふくさんは楽しみながら耕し続けた。
一方、村長の猪本は村人からは、いのさんと呼ばれとても頼りにされていた。
体は小さく力仕事は苦手だが、頭が抜群に切れるからだ。

村経営の責任者であるいのさんが毎年1月に村の未来の計画を立て、ふくさんたち村人がそれを実行するという役割だった。
その計画は、
- 村人の開拓能力
- 隣村との領地のせめぎ合い
この双方を鑑みて、
- 最高の収穫高を手にいれるにはどうすべきか?
- 村人を短期的にも長期的にも幸せが最大化する利益分配
を考え抜いていた。
いのさんが「いつまでにどこまで開拓するか?」を決め、
その決定した計画に沿って、
ふくさんが「どうやって耕すか?」を工夫して実行し報酬を得る。
こうして村はどんどん発展していった。

戦略と戦術の違い
この創作話でもあったように、
「いつまでにどこまで開拓するか?」を決めることが戦略。
「どうやってやるか?」を考え実行することが戦術。
登山が好きな人の例え話で言うと
「いつまでにどの種類のどの高さの山に登るか?」を決めることが戦略。
「どうやって登るか?」を考え実行することが戦術。
ビジネスは旅だ!と思う人は
「いつまでにどこに行くか?」を決めることが戦略。
「どうやって行くか?」を考え実行することが戦術。
ということで。
戦略は、なぜやるのか?何のためにやるのか?どんな成果を得るのか?など組織が進む「方向や方法」を決めること。
戦術は、最短最速で効率よく達成するには?と「手段」を決めること。
どこまでやるかが決まらないと、どうやるかは決まらない。
どこに登るかが決まらないと、どう登るかは決まらない。
どこに行くかが決まらないと、何に乗るかは決まらない。
こんな例えで戦略と戦術についてチーム内の共通理解を深めましょう。
まとめ
さて、話を現在に戻します。
先述のふくさんは、もちろん私のことです。
会社員として働いてきた私は、戦術思考がとても得意でした。
少し卑下した言い方をすると、小手先が死ぬほど器用なのでそれなりの成果を出すのが得意だったとも言えます。
しかしトップとしてスタッフと共に会社を前に進める役割になった今。
必要なのは戦略思考です。
これが経営的視点の考え方そのものと言えるのかもしれません。
正直、この考え方を身につけることは本当に難しい。
戦略と戦術の違いって、サッカーとフットサルぐらいかな?と思ってたんですが、サッカーと茶道ぐらい違いました。
まだまだまだまだまだ足りてない私が言うのもあれですけど、足りない力は教えてもらってトレーニングするしかない。
それでもダメならプロに助けてもらうしかない。
これからもしっかり勉強して成長していきます。
一緒に成長していきましょう。

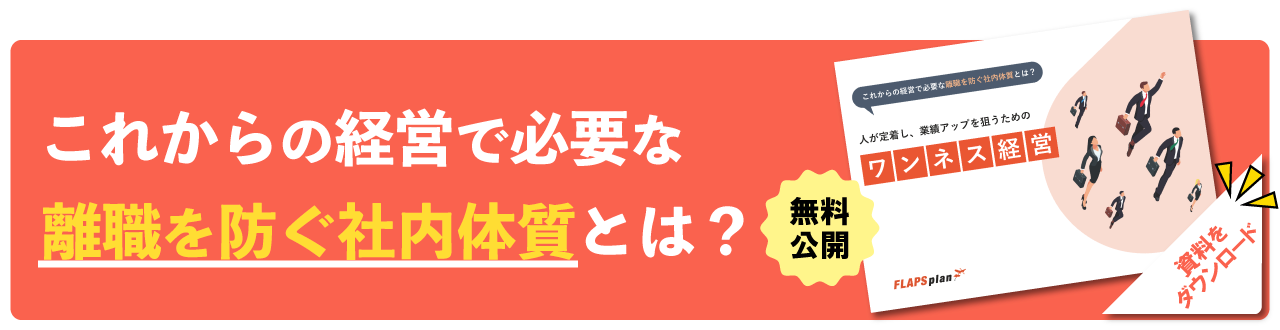
この記事を書いた人
![]()
福永寿徳
大学卒業後、ヘルスケア業界で1000名以上のトレーナーを育成。 セールス下手でも日本の隅々にまで展開することに成功。 好きで得意なことで役に立つと自分も周りも幸せだ。と確信する。 その後、独立起業。インナーブランディングの専門家として活動中。 趣味はトライアスロンだが走るのは嫌い。サウナとバスケ観戦が好き。 焼肉の部位はハラミ。フラップスプランの代表。
関連記事
-

2021.11.23
スタッフを連れて行くならココ!~その1:てっぺん渋谷女道場~
チームづくり〜〜〜研修で東京に行くことにしたけどそろそろコロナも落ち着いてきたことだし懇親会をどこでやろう? せっかく東京に行くんだから普通のお店じゃつまらないよな。〜〜〜 そんな滅多にないレアな悩みにお答えします! 一度はスタッフさんを連れて行きたい!そんなおすすめのお店情報をお届けします! 記念すべき第一弾は渋谷の元気な焼き鳥屋【てっぺん渋谷女道場】さんをご紹介します! おすすめポイント1女性スタッフが輝いて働く職場 「てっぺん渋谷女道場」さんは渋谷駅から10分ほど歩いたところにある焼き鳥屋さんです。 今回、「てっぺん渋谷女道場」さんをおすすめさせていただいた最大のポイントは 料理もさることながら、「女性が輝いて働いてる職場」だということです。 女道場さんはその名の通り、たくさんの女性スタッフさんが働いています。(※男性スタッフもいます。) 特徴的なのはそこで働いているみなさんが笑顔でとても楽しそうに仕事をしているんです! 居酒屋らしいワイワイした雰囲気の中でスタッフさんの笑顔と元気のいい声が飛び交っています。 歯科医院さんなど女性の多い職場の方にとっては年齢の近い女性が楽しそうに働いている姿はきっといい刺激になるはずです。 女道場の元気の秘密 女道場のスタッフさんが元気に楽しそうに働いているのには理由があります。 それが「てっぺんの朝礼」 この朝礼が女道場の元気の源であり一番の特徴でもあります。 朝礼には、誰でも参加することができて企業さんの研修や中学生の修学旅行のコースとして利用されることもあるんです。 実際にやってみるとわかるのですが朝礼が終わるとものすごく明るく元気になります! お時間があれば、ぜひ参加してみてください!詳しくはこちらから→【てっぺんの朝礼】 おすすめポイント2居酒屋で号泣?必見の誕生日イベント もう1つ女道場さんのおすすめポイントはお店全体を巻き込んだ誕生日イベントです! このイベントがとにかくすごいんです。 どのくらいすごいかというと 居酒屋のイベントなのに号泣する方もいらっしゃるくらい(°°) 詳しいことは実際に行ってからのお楽しみです! 一緒に行く方で前後1ヶ月にお誕生日の方がいたら電話予約の際に伝えてみてください! お店の雰囲気 実際の雰囲気がわかるムービーもあるのでぜひご覧ください。 https://youtu.be/u-ZNyJzCmuQ まとめ 女性スタッフの元気をもらえる接客感動の誕生日イベント この2つが女道場さんのおすすめポイントです! お料理の話が出なかったですが焼き鳥もすごく美味しいです! ぜひ一度職場の皆さんで足を運んでみてくださいね! てっぺん渋谷女道場の食べログページ↓↓↓https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130301/13019857/ 今後もスタッフさんを一度は連れて行きたいそんなお店のご紹介をしていきます! お楽しみに!
-

2023.11.07
サーバントリーダーシップとは?概要や注目されている背景について紹介
チームづくり近年、リーダーとメンバーとの信頼関係を構築するための手法として、「サーバントリーダーシップ」に注目が集まっています。 メンバーの自主性をより促すためトップダウン型からの変革を考えた場合、サーバントリーダーシップの導入は大変有効です。 また、シェアドリーダシップとの関連で興味を持っているという方も多いのではないでしょうか。 今回は、サーバントリーダーシップの概要や従来の支配型リーダーシップとの違いを解説し、今注目されている背景をご紹介します。 サーバントリーダーシップの概要 「サーバントリーダーシップ」は、「奉仕の精神で部下に接し、導く」という考え方をもとにしたリーダーシップ理論です。 1970年、ベトナム戦争の泥沼化やウォーターゲート事件などを時代背景に、アメリカのロバート・K・グリーンリーフ氏がヘルマン・ヘッセの短編小説「東方巡礼」から着想を得て提唱しました。 「サーバント(servant)」という言葉には、召使いや奉仕する人という意味があり、サーバントリーダーシップは「奉仕型」のリーダーシップと言うことができます。 リーダーが部下に対する傾聴の姿勢を持ち、自主性を認めながらそれぞれの能力の最大化を図ることで、目的を達成するというスタイルが特徴と言えます。 そのため、組織において協力し合う関係が生まれやすい点がメリットです。 従来の支配型リーダーシップとの違い 従来の「支配型リーダーシップ」は、明確な上下関係と強い統率力に基づくリーダーシップで、リーダーがトップダウンで指示や命令を出し、それに部下が従うことで目標を達成してきました。 一方、サーバントリーダーシップでは、リーダーが部下の話をしっかり傾聴することで関係を築き、ともに協力し合いながら目標を達成します。 また、リーダーが部下に対して支援を行うことで信頼が得られる点もサーバントリーダーシップの特徴です。 サーバントリーダーシップの発揮によって、部下の強みや自主性を引き出し、積極的な行動へ導くことが可能です。 従来の支配型リーダーシップは恐怖心や義務感で部下を行動させるという点が大きな特徴ですが、サーバントリーダーシップでは部下との信頼関係を大事にすることで部下自身が考えて行動するようになります。 このように、サーバントリーダーシップは、これまでの支配型リーダーシップとは正反対の考え方と言えます。 注目されている背景とは? 経済成長が著しかった時代では、リーダーが強い意志や価値観を貫くことで部下を強力にけん引していくスタイルが主流でした。 しかし、現在は、不確実で予測が困難な「VUCA時代」に突入しており、ビジネス環境が大きく変化し、顧客ニーズも多様化しています。 このような時代の中で企業が成長していくためには、不測の事態に柔軟に対応できる組織づくりが欠かせません。 リーダーがすべてを管理して意思決定していく従来のスタイルでは対応が遅れてしまうため、メンバー一人ひとりが主体性を持った組織にしていく必要があります。 また、必ずしも一人のリーダーの意見が正しいとも言えないことから、さまざまな経験や知識を持った人材の活用が求められます。 そのため、サーバントリーダーシップによって、個性を発揮しながら行動できる人材を育成することが重要です。 まとめ サーバントリーダーシップは、「奉仕の精神で部下に接し、導く」という考え方をもとにした「奉仕型」のリーダーシップ理論です。 傾聴などを行って部下との信頼関係を築き、部下自身が考えて行動するように促すのが特徴で、リーダーが部下に命令や指示を出して統率する、従来の支配型リーダーシップとは大きく異なります。 不確実で先が読みにくいVUCA時代において、サーバントリーダーシップは企業の成長に不可欠な考え方だと言えます。 ぜひ、自社へのサーバントリーダーシップの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
-

2025.03.12
仕事ができる人とは?具体的な特徴や仕事ができない人との違いを解説
チームづくり企業が成長していくためには「仕事ができる人」の存在が欠かせません。 そのため、部下への指導や人材育成をする上で、実際に仕事ができる人の特徴を知りたいと考えている方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、仕事ができる人の具体的な特徴や、仕事ができない人との違いについて解説します。 ぜひ、参考にしてみてください。 仕事ができる人とは 「仕事ができる人」とは、業務を効率的にこなすのはもちろん、積極的な姿勢で行動し、周りの期待を上回る結果を出せるような人のことです。 ビジネス用語では、こうした人材を「敏腕」と呼んでテキパキした仕事ぶりを評価したり、「優秀」「有能」と能力の高さを認めたり、あるいは「腕が立つ」と技術面での卓越性を表現したりします。 ただし、仕事ができる人として周りから評価される基準や要素は、年齢などで異なります。 キャリア初期では実務能力や自発性が重視され、上の立場になるほど人を動かす力や調整能力が問われるようになるケースが多いです。 仕事ができる人の具体的な特徴 仕事ができる人の具体的な特徴として挙げられるのは、下記の5つです。 主体的に行動できる 優れたリサーチ力と学習意欲を持つ 問題点を見出す力に長けている 自己管理能力が高い 客観的に判断できる それぞれ解説します。 主体的に行動できる 仕事ができる人は、考えるだけでなく実行にすぐ移せるといった行動力を持っています。 どんなに素晴らしいアイデアも行動に移さなければ価値を生みません。 変化の激しい現代社会では、自ら考え動く能力が重要視されています。 また、必要なときに適切な人に協力を仰いだり、未知の領域でも積極的に情報を求めたりする姿勢も必要です。 自分の力だけでなく、周囲のリソースを活用できる人は仕事で成果を出しやすいです。 優れたリサーチ力と学習意欲を持つ 依頼された業務に関する情報を素早く適切に集められる情報収集力の高さも特徴の一つです。 加えて、自分の知識不足を認識した場合、自発的に学びを深める行動ができることも重要です。 常に新しい知識を吸収しようとする姿勢が、長期的な成功を支えます。 問題点を見出す力に長けている 仕事ができる人は、日常業務の中で常に改善点を模索し、より良い結果を追求しています。 なぜなら、現状を正確に把握したうえで、問題点を見出す力を持っているためです。 問題が表面化する前に察知し、先手を打てる人材は企業にとって大きな資産となります。 自己管理能力が高い 自分自身をコントロールする能力も特徴として挙げられます。 特に仕事のパフォーマンスを左右するのは、時間管理、感情・モチベーションの調整、健康管理の3つの要素です。 困難な状況でも冷静さを保ち、自分のベストコンディションを維持できる人は、長期的に安定した成果を出し続けることができます。 客観的に判断できる 仕事のできる人は、主観や感覚ではなく、数字やデータに基づいた判断ができます。 たとえば、販売データを分析して優良顧客を特定したり、数値目標の進捗をチェックして早期に課題を見つけたりと、常に客観的な視点を持っているのが特徴です。 このような事実に基づく判断は、チームからの信頼を得やすく、具体的な成果にもつながります。 仕事ができる人とできない人の違い それでは、仕事ができる人と仕事ができない人にはどのような違いがあるのでしょうか。 主な3つの観点から解説します。 当事者意識・責任感 仕事ができる人は、どんな業務も他人事ではなく自分事としてとらえます。 また、自分の行動がどのような影響を与えるのかを考え、責任を持って取り組んでいます。 一方、仕事ができない人は、問題が起きても「自分には関係ない」と放置したり、「とりあえずやっておけばいい」という姿勢だったりするなど、言われた通りに最低限の業務をこなすだけです。 こういった当事者意識や責任感の有無の違いが、成果の差となって表れます。 周囲との関係性 仕事ができる人は、周囲との関係をしっかり築けています。 たとえば、進捗状況を定期的に共有したり、メンバーの意見を積極的に取り入れて全員が同じ方向を向けるよう働きかけたりします。 また、自分にできることは責任を持って対応しながら、必要に応じて適切に助けを求められる絶妙なバランス感覚も持ち合わせているのです。 対照的に、仕事ができない人は周囲との関係をうまく築けておらず、一人で抱え込むか、逆にすべてを人任せにしてしまいます。 報告や相談を怠ることで、トラブルも招きがちです。 失敗への向き合い方 仕事ができる人は、失敗を恐れません。 むしろ失敗を成長の機会ととらえ、「なぜ失敗したのか」を客観的に分析したうえで、具体的な改善策を立て、同じミスを繰り返さないよう実践します。 さらに、そこで得た教訓を周囲と共有し、企業の成長にも貢献します。 一方、仕事ができない人は失敗の原因を外部に求め、「環境が悪い」「運が悪かった」などと言い訳しがちです。 表面的な謝罪で済ませ、本質的な改善に取り組もうとしない姿勢が、成長の機会を逃す結果となっています。 まとめ 仕事ができる人の特徴は、主体性を持って行動し、優れた情報収集力と問題解決能力を備え、自己管理と客観的判断ができることです。 また、仕事ができない人との大きな違いは、当事者意識の有無、周囲との関係構築力、そして失敗への向き合い方にあります。 仕事ができる人に成長してもらうには、これらの特徴や違いを理解しておくとよいでしょう。
私が変わると、チームが変わる
ワンネス経営®プログラムは、インナーブランディング強化というアプローチを通して、 お客様企業が求める成果を達成していくという「新しいチームビルディングのプログラム」です。 イメージが持ちづらい点があるかもしれませんが、どうぞお気軽にご質問、ご相談ください。