Column
2022.10.27
チームづくりのお作法
チームづくり

目次
チームづくり、チームビルディングに興味がある方へ
とにかく情報が多いこの時代にこのブログに辿り着いていただきありがとうございます。
めちゃくちゃ勉強になった〜とか、役に立った!とか言ってもらえるかはわかりませんが、読んで損した〜、とか読むんじゃなかった〜とは絶対にならないのでぜひ最後までお付き合いください。
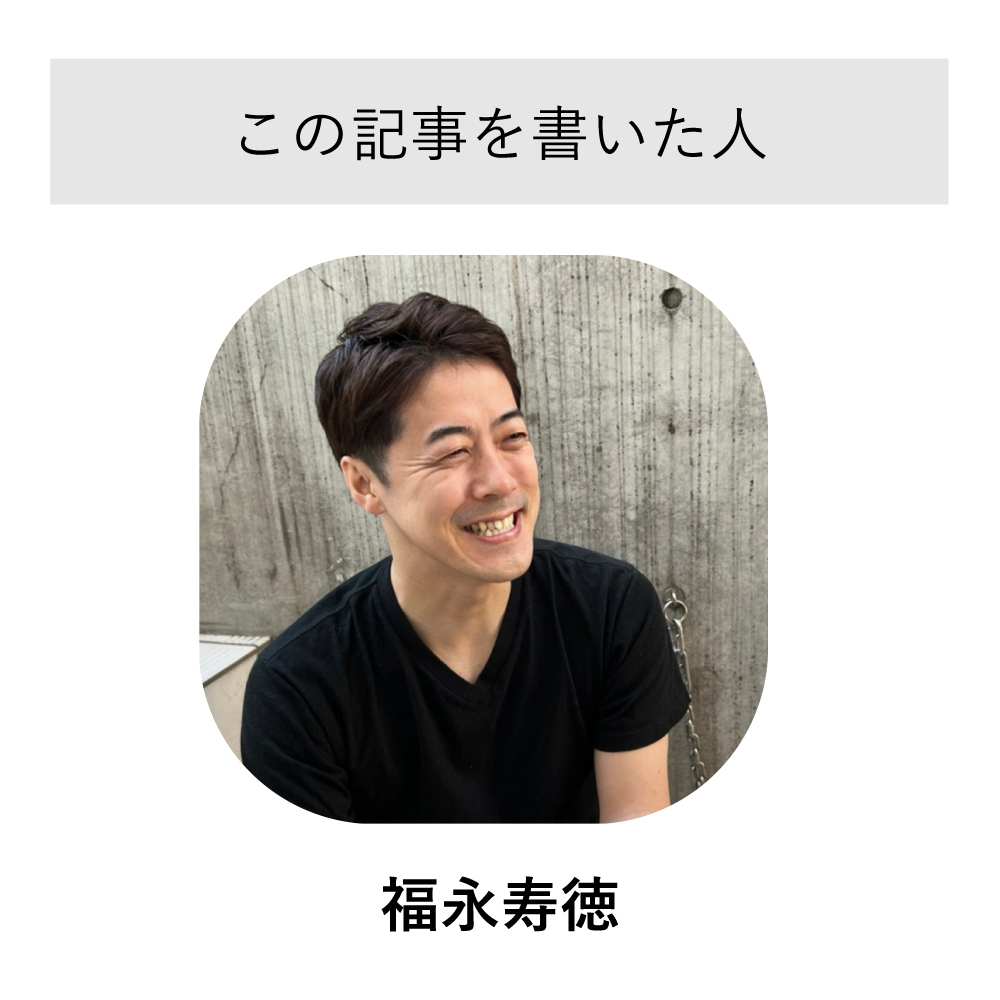
大学卒業後、ヘルスケア業界で1000名以上のトレーナーを育成。 セールス下手でも日本の隅々にまで展開することに成功。 好きで得意なことで役に立つと自分も周りも幸せだ。と確信する。 その後、独立起業。インナーブランディングの専門家として活動中。 趣味はトライアスロンだが走るのは嫌い。サウナとバスケ観戦が好き。 焼肉の部位はハラミ。フラップスプランの代表。
概要 チームづくりには手順がある
茶道、華道、柔道、弓道…
あらゆる求道の世界には初心者が学ぶべき「お作法」があります。
それはきっと終わりのない探求の旅に出るというハードルを少しでも下げるための手順なのではないでしょうか。
同様にチームビルディングという終わりのない種目にもお作法があります。
それは人と人とが関わり合い相互に協力し成果を出す。
改めて考えてみれば、かなり難易度の高いことです。
しかも、もうあるチームを活性化するのか、新たに人が加わるのか、スタートアップのように全員が初めましてなのか。
一口にチームビルディングと言っても、その置かれている状況によって全く違うアプローチが必要だったりします。
このように終わりも正解もないわけで、ある意味「道」的ともいえます。
ゆえに外してはいけない手順が存在するわけです。
それがこちら
- チームが大切にしていることを大切にする
- 個人のスキルアップ
- 個人のマインドアップ(あり方・リーダーシップ)
- チームの信頼関係、心理的安全性の構築
- チームで本質的なフィードバック、アドバイス、リクエストができる
- リーダーが経営理念、ビジョン、目標を理解し伝えられるようになる
- 定期的に共通の学びなど時間の共有や改善機会を設け継続する
今回は「とある会社の営業部」を例に各項目について解説していきます。
各論
1.チームが大切にしていることを大切にする
これは採用の段階と言えます。
ある意味、一番重要なのかもしれません。
どんな人でもどんとこい!という業務のシステム化がされていたり、教育体制が整っていれば問題ないのですが、そんなチームはあまり存在しません。
例えばチームで大事にしているのは「協力」と言っているのに人と協力するのが絶対に嫌いな人が入ってくると双方にとって不利益だったりします。
具体的な取り組みとして
- 明文化されているルールや規則を理解し遵守する
- 明文化されていない雰囲気、風土を作っている共通言語を理解する
この二つがチームに参加させるかどうか?の段階で約束し、実践できるかがとても大切です。
2.個人のスキルアップ
次に取り組むことは、新しく入った人に業務の中でスキル系の教育です。
一部分であろうが、少しであろうが業務の一端を任せられる状態を先に作ります。この段階での、あり方であったり、仕事への取り組む姿勢であったりというのは最低限で構いません。
なぜなら、まずは本人が「他者の役に立つ」感覚を持てること、そして周囲からもそのように認識されることがとても大切です。
なぜなら、仮に誰よりも早く出社して、みんなのデスクを拭くといった貢献活動をしていても、実際の責任業務の中で自分が役に立てている感覚が持てないとそのチームの中での自己重要感が持てないからです。
3.個人のマインドアップ(あり方・リーダーシップ)
そして、いよいよ心の成長が求められます。
もちろんスキルアップと同時でも構いません。
しかしながら、ここが人材育成の最大の関門と言えます。この方法がわからない、できないことによって、社内教育の限界を感じ外部研修などを活用していくことになります。
もちろん、採用の失敗は教育では取り返せないという言葉の通り、採用で半分は決まっている部分もあるでしょう。しかし、教育によってこの壁を突破した事例は無数に存在します。
個人のマインド、心の成長にどのように取り組むかが、これからの時代の経営において最重要課題となるのではないかと予想しています。

4.チームの信頼関係、心理的安全性の構築
自分を知り、他者を知る段階です。
価値観の違いを認め合い、同じ方向に向かう仲間として認識を新たにしていきます。
ただの仲良しグループではなく、高い成果を目指すプロ同士としてのコミュニケーションを取るための準備段階です。
5.本質的なフィードバック、アドバイス、リクエストができる
前段階を経て、相手に対して本当に大切な情報を伝えることができるようになる必要性があります。
フィードバックとは、事実について感想を伝えること。
アドバイスとは、個人的な体験に基づき行動変容を促すこと。
リクエストとは、もっとこうなって欲しいとニーズを伝えること。
例えば、同じチームの先輩に対して「いいことだと思う」というフィードバックは誰でもできますが、「それは悪いことだと思う」ということをまっすぐ伝えられる後輩はなかなかいません。しかし、それこそが強いチームに必要な関係性です。
多くの人が「いい人」でありたいので、意見をまっすぐ伝えられない。という病にかかっています。そして、伝える勇気のない自分のことは棚に上げて、「ストレス」と呼び換えているのです。ここのフェーズはとても大切です。
6.経営理念、ビジョン、目標を理解し伝えられるようになる
特にリーダーとなる人は目指す必要性があります。
経営者の熱量100が末端スタッフに100として届くことはありません。
だから経営者は200とか300の熱量で話すのですが、それでも限界があります。
そのために、途中でその熱量を中継してくれるスピーカーが必要なのです。
これこそが中間管理職の真の役割と言えます。

7.定期的に共通の学びなど時間の共有や改善機会を設け継続する
人間は忘れる生き物です。
信じられないぐらい忘れます。昨日の昼ごはんすら覚えているか怪しいものです。
私は1週間前に履いていた靴下の色なんて確実に覚えていません。
ですから、常に意識させる必要性があります。
日常の中でいかに共通言語を使っていくか。学びで得たノウハウを活用するか。
そっくりそのまま継続力という言葉につながり、学びの日常的な活用度合いこそが長期的成果につながる重要指標とも言えます。
だからこそ定期的なM T Gや復習など仲間同士の時間の共有が大切になるのです。

まとめ
いかがだったでしょうか?
ご自身のチームはどの段階でしょうか?
人間は感情の動物です。
メンバーとの距離が近すぎて客観的視点で見れないこともしばしばあるでしょう。
「自分はできてるのにメンバーの能力が低いせいでうまくいかない」
「自分はちゃんと伝えているのにメンバーが受け取らない」
まずはそこを認めて、感情と事実を分けて考えてみてください。
現状を正しく認めることができれば、必ず前に進めます。
チームビルディングの手順を大切にして最強で最高のチームを作っていきましょう!


この記事を書いた人
![]()
福永寿徳
大学卒業後、ヘルスケア業界で1000名以上のトレーナーを育成。 セールス下手でも日本の隅々にまで展開することに成功。 好きで得意なことで役に立つと自分も周りも幸せだ。と確信する。 その後、独立起業。インナーブランディングの専門家として活動中。 趣味はトライアスロンだが走るのは嫌い。サウナとバスケ観戦が好き。 焼肉の部位はハラミ。フラップスプランの代表。
関連記事
-

2024.12.31
人材マネジメントを取り入れるには?具体的な手法や事例を紹介
チームづくり人材マネジメントは、組織のビジョン達成に向けて人材の管理や活用を行うアプローチです。 導入によって企業にさまざまなメリットがありますが、具体的な手法や事例を知りたいという方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、人材マネジメントの具体的な手法と2つの事例を取り上げて解説します。 ぜひ、参考にしてみてください。 人材マネジメントの具体的な手法 人材マネジメントの具体的な手法は、下記のとおりです。 課題の把握 必要な人材要件の定義 アクションプランの策定 実行とモニタリング 評価と改善 それぞれ解説します。 1.課題の把握 初めに、組織の成長や発展を妨げている人材面での課題を正確に把握します。 具体的には、営業力の不足による売上の伸び悩みやマネジメント層の不足による組織拡大の限界、従業員の定着率の低さなど、経営に直接影響を及ぼす問題点を特定します。 この段階での課題認識がその後の施策の効果を大きく左右するので、しっかり把握することが重要です。 2.必要な人材要件の定義 課題が明確になったら、その解決に必要な人材像を具体的に描き出します。 求められる能力やスキル、経験値を詳細に定義し、必要な人数も算出しておくとよいです。 また、定着率の向上が課題の場合は、離職の根本的な原因を分析した上で、社内コミュニケーションの改善やキャリア支援制度の構築など、具体的な対策を検討します。 3.アクションプランの策定 人材施策を実現するための具体的なアクションプランを立案します。 採用計画であれば、採用時期や人材要件、採用人数などを設定しましょう。 人材育成においては、研修時期や対象者の選定、教育手法、到達目標などを明確にします。 これらの計画は、関係する部門長や対象となる従業員と共有し、全体の合意を得ることが大切です。 4.実行とモニタリング 策定したアクションプランを着実に実行に移します。 この際、現場任せにするのではなく、経営層も積極的に関与しながら、進捗状況を定期的にチェックする必要があります。 特に初期段階ではきめ細かなモニタリングを行い、計画と実態のずれが生じていないか確認することが重要です。 5.評価と改善 状況と成果を定期的に評価し、目標達成度を測定します。 進捗に遅れが見られる場合や期待される効果が得られていない場合は、その原因を分析し、必要に応じて計画の修正や新たな施策の追加を行います。 より効果的な人材マネジメントのためには、このPDCAサイクルを継続的に回すことが大切です。 人材マネジメントの事例 ここでは、人材マネジメントの事例として、楽天グループ株式会社と株式会社オリエンタルランドの例を紹介します。 楽天グループ株式会社 楽天グループ株式会社では人材マネジメントの改革を推進しており、中でも特に注目される取り組みが「Back to Basics Project」です。 このプロジェクトでは「勝てる人材、勝てるチームを作る」という基本目標を達成するため、次の3つの領域での改善に注力しています。 採用 採用プロセスの見直しや採用ブランディングの強化を行い、より多くの優秀な人材を確保するとともに、採用ランキングの向上を図っています。 この取り組みによって、企業の成長に適した人材が効率的に確保されています。 育成 従業員育成のため、全社的に1on1ミーティングを導入しています。 また、管理職向けのフィードバックスキル向上研修のほか、新たに38の集合型研修プログラムを開発し、90%以上の高い満足度を得ています。 定着 従業員の定着を促すため、評価や報酬制度を刷新し、長期就労者向けの退職金制度も新設されました。 また、在宅勤務制度やフレックス制度など、多様な働き方に対応する仕組みも整備されています。 加えて、「人材育成マップ」を作成し、楽天で積み重ねられるスキルやキャリアを明確化することで、従業員が長期的なキャリアビジョンを描きやすくしています。 従業員の出身国・地域が100を超えるという多様なバックグラウンドを活かし、オープンでイノベーティブな企業文化を醸成しているのも楽天グループの大きな特徴です。 このような取り組みを通じて、従業員が最大限の力を発揮できる環境を提供し、事業の成長を支えています。 参照:楽天グループ株式会社 株式会社オリエンタルランド 東京ディズニーランド・リゾートの運営を手掛ける株式会社オリエンタルランドは、卓越したサービス品質で高い評価を得ている企業です。 同社の優れた顧客満足度の背景には、独自の人材育成制度があります。 特に注目すべきは「ファイブスター・プログラム」という取り組みで、これは従業員(キャスト)の優れた行動を即座に評価・称賛する仕組みになっています。 具体的には、キャストが模範的な行動を示した際に、上司から特別なカードが贈られ、その場で称賛を受けるというものです。 この直接的な評価システムにより、キャストは自身の働きが正当に認められていると実感し、さらなる向上心とやりがいを見出せます。 また、「スピリット・オブ・東京ディズニーリゾート」や「サンクスデー」といった制度も導入されており、組織全体で高品質なサービス提供を支える体制が整えられています。 参照:株式会社オリエンタルランド まとめ 人材マネジメントは、組織の持続的な成長と発展に必要なアプローチです。 その実践においては、課題把握から評価・改善までの体系的な方法が重要となります。 楽天グループやオリエンタルランドの事例が示すように、効果的な人材マネジメントは企業の競争力向上と従業員の成長・満足度向上の両立を可能にします。 ぜひ、これらの手法や事例を参考に、人材マネジメントの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
-

2022.05.31
なぜ教えたのにできないのか?〜教えるとできるの間にあるもの〜
チームづくり「え?この前…教えたよね?なんでできないの?」 って言いたくなる時ありますよね。 というか、よく言っていますよね。 「ウソでしょ???なんでこうなったの??」 って言いたくなる場面にたまに出くわしますよね。 さて、なぜ人は教えたのにできないのか。 ついつい 能力が低い意識が低い真剣じゃない本気じゃない覚悟が足りない など 相手の足りないものに目が向きがちです。 しかし、そこに焦点を当てても一向に状況は良くなりません。 今回は、本質的な問題解決を目指すために、 なぜ教えたのにできないのか?について鋭く優しくメスを入れていきます。 大学卒業後、ヘルスケア業界で1000名以上のトレーナーを育成。 セールス下手でも日本の隅々にまで展開することに成功。 好きで得意なことで役に立つと自分も周りも幸せだ。と確信する。 その後、独立起業。インナーブランディングの専門家として活動中。 趣味はトライアスロンだが走るのは嫌い。サウナとバスケ観戦が好き。 焼肉の部位はハラミ。フラップスプランの代表。 投稿一覧へ 教えたのにできないとイラッとくるのはなぜ? そもそも、教えたのにできない理由は何かというと、基本的には「忘れるから」です。 逆に質問ですが、あなたは3日前の夜ごはんはなんだったか覚えていますか? 私は、さっぱり思い出せません。 頭の中で探っても出てきません。 たまたま誰かとの食事会だったから、とかがないと絶対に無理です。 むしろそれですらカレンダーを見て、3日前は◯曜日だったからえーっと。。 っていう感じです。 人間の記憶なんてそんなものです。 どれぐらい人間が忘れるかというと、これぐらいです。 しかも、厄介なのは教える側は覚えているのですが教わる側が覚えていないことがよくあること。 なぜなら、教える側は記憶から引き出して伝えているので、記憶が強化されてます。 しかし、教わる側は新しい情報なのでとても定着が浮動的です。 いや、そうは言っても仕事のことなんだから、 「普通にちゃんとやっていれば忘れない!」 「そんなに難しいことはやらせてないはず!」 と言いたくなると思います。 そうなんです。そろそろお気づきでしょうか。 相手が忘れてしまったことにイラッときているのではないのです。 そもそも教えている時にメモを取ったりしていたのか? 分からないことがあった時、そこで質問していたのか? さらに今のご時世、業務によってはスマホで撮影すれば何度でも学べるのに、そういう工夫や努力はしたのか? と、忘れていることではなく、教えてもらった際の取り組む姿勢まで遡って、「ほらな、やっぱりあの時理解してなかったんやないか〜!」と、【教えた自分の労力が無にされた】とイラッとしてしまっていることが大半です。 なぜなら(あなたに普通の人間の感情があれば)相手がものすごく真剣に理解しようとして、一生懸命取り組んで、それでもできないのだったら、それはもう「経験が足りないね」とか「続けたらできるよ」とか「私も昔そうだった」とか、前向きな声かけをしたくなるはずですからね。 教えたのにできない理由 全6パターン ということで、まずは教えたのにできない理由を明らかにしていきます。 私が出会ってきた「あれ?教えたのにできてないの?」の全6種類のパターン。 おおよそのできない理由を網羅しているはずです。 こちらで冷静に「現象」を把握していきましょう。 1.教えてもらったこと自体を忘れている 状態:できない 「あれ?前に教えたよね?」の回答 →「あれ?習いましたっけ?」 解説 これはむしろ清々しいですね。 その時間全ての存在を忘れてしまっているわけですからね。 教えた上司の名前を覚えているかも怪しいですね。 ただし、教えてからあまりにも時間が経過するとあり得る状況です。 2.教えてもらったことは覚えてるけど内容を忘れている 状態:できない 「あれ?前に教えたよね?」の回答 →「あれ?どうやってやるんでしたっけ?」 解説 これは意外と多いパターンだと思います。 ただただ、記憶定着していないので繰り返して教えるしかありません。 やってみせ言って聞かせてやらせてみて、誉めてやらねば人は動かじ。 という山本五十六先生の教え通りに根気よく伝えましょう。 3.間違って覚えている 状態:正しくできない 「あれ?前に教えたよね?」の回答 →「あれ?違いましたっけ?」 解説 これは腹立たしいパターンですよね。いい感じで淀みなくやってるな。と思ったら全然違う結果になってるやつです。この状態で顧客とのやり取りをしていると非常に危険な状態と言えます。 4.おぼろげに覚えていて間違える 状態:正しくできない 「あれ?前に教えたよね?」の回答 →「あれ?何か違ってました?」 解説 これもまたちょっとリカバリーが大変なやつです。本人の中で8割ぐらいは自信があるわけですからね。だから指摘しても「あ、それか〜」など、実際はまあまあ違うのに、さも一部分であるかのように取り繕い、反省の弁が全く聞こえてこないパターンとも言えます。 5.正しく覚えているのにその通りやらない 状態:正しくできない 「あれ?前に教えたよね?」の回答 →「あれ?ちゃんとやったのになんでだろ?」 解説 これもまた、軌道修正が大変なパターンです。謎の自信がマニュアルを無視したり、オリジナリティを生み出したりします。パソコンを疑う前に自分を疑え!相手を疑う前に自分を疑え!と言いたくなります。 ⒍覚えてないし、できないのに「できる」と言ってしまう 状態:調べるけど結局できない 「あれ?前に教えたよね?」の回答 →「あれ?できると思ったんですけど」 解説 できないと言えない、弱いところを見せられない自分の問題だったり、その発言を許容しない周りの環境だったり。色々理由はあるけれど、Google先生がなんでも解決策を知っていると、盲信してしまっていると陥りがちな状況。 解決策はあるのか? イラッとしてしまう本質的な理由は相手が忘れるのではなくて、真摯に取り組んでいるか?という姿勢に対して。 そして、教えたのにできない全パターンも明らかになりました。 さあ、いよいよ抜本的解決です。 本当にそんな解決策はあるのか?とどれだけ調べても勉強しても考察しても最後に残るのは 根気 これしかありません。 どれだけ褒めようが叱責しようが、ご褒美や罰を作ろうが、本人がその気にならない限り変わりません。 どれだけわかりやすい手順書、マニュアルを作っても本人が見なければその通りにはいきません。 あらゆる、精神的、物理的アプローチを凌駕するのが根気なのです。 教育とはよく言ったもので。 教える+育む でできています。 私たちはつい、教える=できる。と思っていますし、信じています。 しかし、覚えて実行する。というのは実はなかなか難しいことをやっているのです。 繰り返しになりますが、できていて教える側には、習慣的なものであっても、初めての人には難しい可能性があるのです。 だからこそ、教えたのちに【育む】という期間を持つ必要があります。 育む期間は不安定な状態です。 つまり、この期間に質問したり確認したりうまくできなかったり、というのは想定内として指導していくのです。 うまくできない期間がある。 教える側がこのように認識することで、精神衛生上も良い環境で指導することが可能になります。 今、当たり前にできている自分にも、 うまくできなかった時期はなかっただろうか? そんな自問自答をすると、少しだけ優しく見守ることができるかもしれません。 まとめ 教えたのにできない。 は決して相手に何かが欠如しているだけとは限りません。 こんな考察ができたのも、恥ずかしながら時には私自身もイラっとしてしまうこともあるからです。 気づき、行動を変えていくしかありません。 私たちワンネス経営チームがサポートに入る際、大切にしている原理原則があります。 それは、私が変わるとチームが変わる。という言葉です。 この原則を真ん中に置いて、まずは自分に変えられることはないか?と考えてみることが大切です。 教育や指導の目的は、相手のできない部分を突きつけてあなたが勝利していい気分になることではありません。 より高い成果を出すことです。 感情的な対応ではなく、共に大きな成果を出すために、厳しくとも心は穏やかに、教え育んでいきましょう。 良い事知ったで終わらないために 継続するには、まず忘れない事が大切です。 なぜなら正しく覚えていないと使う事ができないからです。 その証拠に、わたしたちが九九を使って便利な生活が送れているのは、九九を正しく覚えているからです。 日々思い出すために、定期的に情報を受け取る事が効果的です。 是非ワンネス経営®︎公式ラインにご登録ください! 事務局:スズキヒラク ワンネス経営®︎公式LINEを追加!
-

2022.12.06
コンプライアンス研修とは?意味や目的、内容を詳しく解説
チームづくり企業リスクが大きい不祥事を未然に防ぐため、最近ではコンプライアンス研修を取り入れるケースが増えてきています。 すでにコンプライアンス研修の導入を決めているものの、どのような研修なのか基本的なことから知りたいと思っている方も多いかもしれません。 このような方に向けて、本記事ではコンプライアンス研修の意味や目的をはじめ、どのような例がコンプライアンス違反に該当するのかを詳しく解説します。 コンプライアンス研修の概要 そもそも「コンプライアンス」は、日本語で「法令遵守」を意味する言葉ですが、法律だけでなく、倫理や社会規範などその対象は広範囲に及ぶ点が重要です。 そこから、コンプライアンス研修とは、企業の不祥事防止や価値向上のため、仕事に関連する法律や規律、コンプライアンスの重要性などを学ぶ研修のことを指しています。 企業には、法令遵守はもちろんのこと、社会からの信頼にもしっかり応える必要があると言えます。 社員一人ひとりがコンプライアンスについて学ぶことで、企業全体の意識も向上するでしょう。 コンプライアンス研修の目的 コンプライアンス研修には、どのような目的があるのでしょうか。 主な目的として下記の3つが挙げられます。 コンプライアンス知識の理解 コンプライアンス違反へのリスクヘッジ 企業の価値向上 それぞれ説明していきます。 コンプライアンス知識の理解 コンプライアンス研修では社員全員がコンプライアンスの知識を理解し、身に付けることが大きな目的となっています。 新入社員はもちろん、どのような法律や社会規範があるのか正確にわからない社員も多いはずです。 違反になるとは知らなかった、というケースもあるため、全員で基本的な知識や遵守する対象を学び、社内でのコンプライアンス認識を共有しておかなければいけません。 また、理解不足による違反を防ぐには、研修を定期的に行い、法律改正や社会状況の変化に合わせて知識をアップデートする必要があります。 コンプライアンス違反へのリスクヘッジ コンプライアンスに違反することで、社会的信用を失いかねない事態に陥ります。 社員一人ひとりがコンプライアンス違反による危険性を学び、認識を共有することで、企業のリスクヘッジにつながります。 また、身に付けた知識によって、コンプライアンス違反の予兆を早期に発見したり対処したりすることが可能です。 企業の価値向上 企業の価値を高めることも、コンプライアンス研修の目的の1つです。 コンプライアンスを遵守して企業の社会的責任を果たすことで、企業価値が向上し、信頼が得られます。 社員はこのような自社に誇りを持ち、一員としての意識のもと、目標に向かって仕事に取り組めるようになります。 その結果、コンプライアンス意識をより向上させるといった好循環が生まれ、健全で成果の上げやすい企業経営が実現できるのです。 コンプライアンスの違反例 そもそも、コンプライアンスの違反例にはどのようなものがあるのでしょうか。 コンプライアンス研修を行うにあたって、どのようなものがコンプライアンスの違反になるのか知っておくと良いです。 代表的な例が下記の3つになります。 ハラスメント 個人情報流出 法的な違反 それぞれについて解説します。 ハラスメント 「ハラスメント」とは、迷惑行為によって相手を不快にさせたり尊厳を傷つけたりすることを指し、いわば「嫌がらせ」「いじめ」と同義の言葉です。 企業において気をつけるべきハラスメントとして、「パワーハラスメント」や「セクシャルハラスメント」が挙げられます。 特に、度を超えた叱責や過大な要求など業務上の優位性を使って相手に苦痛を与えるパワーハラスメント(パワハラ)は、どこでも起こり得る問題の一つです。 2022年4月からは、パワハラ防止法施行に伴い、パワーハラスメント防止措置が全企業に義務化されています。 そのため、パワハラの内容を社員全員が理解しておく必要があります。 参考:職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!|厚生労働省 都道府県労働局雇用環境・均等部(室) 企業のハラスメントでは、「そんなつもりじゃなかった」「以前は問題なかった」と無自覚で行っているケースが多いため、研修でどのような行為が該当するのかを理解してもらい、自覚を促すことが重要です。 個人情報流出 ネットワーク上での情報管理・共有が増えてきた昨今、個人情報流出も多くの企業でコンプライアンス違反となる可能性が高いです。 企業でよく発生するのが、マルウェアなどの悪意を持ったプログラムがパソコンに侵入することで、個人情報が盗まれたり、不正利用されたりするケースです。 個人情報の保護に関する法律により、企業には個人情報の適切な管理が義務付けられているため、社員一人ひとりの意識が大切になります。 参考:個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)|個人情報保護委員会 ウイルス対策ソフトの導入や適切なパスワード管理で、情報流出をしっかり防止しなくてはいけません。 法的な違反 コンプライアンスのことを「法令遵守」と言うように、コンプライアンスの中で大きな割合を占めるのが法律です。 商品の開発・販売やサービスの提供といった企業活動を行うには、「著作権法」や「法人税法」といったさまざまな法律を遵守する必要があります。 また、顧客や社会に向けたものだけでなく、企業内に向けた「男女雇用機会均等法」や「労働基準法」「労働安全衛生法」などの法律も遵守の対象です。 自社の活動にどのような法律が関係しているのか、的確に把握しておくことが重要です。 まとめ コンプライアンスには、法律だけでなく、倫理や社会規範なども含まれているため、遵守するにはさまざまな観点からの学びが必要です。 コンプライアンス研修によって社員一人ひとりがコンプライアンスの知識を理解し、リスクを意識することで、将来的に企業の価値が向上します。 ぜひ、コンプライアンス研修の導入を検討してみましょう。 [sitecard subtitle=関連記事 url=https://flapsplan.co.jp/blog0160/ target=] [sitecard subtitle=関連記事 url=https://flapsplan.co.jp/blog0158/ target=]
私が変わると、チームが変わる
ワンネス経営®プログラムは、インナーブランディング強化というアプローチを通して、 お客様企業が求める成果を達成していくという「新しいチームビルディングのプログラム」です。 イメージが持ちづらい点があるかもしれませんが、どうぞお気軽にご質問、ご相談ください。