Column
2021.09.07
グループとチームの違い
チームづくり

強いチームを作りたい。
そう思ったなら強いチームとは一体なんなのか?という定義を明らかにしておくことが重要です。
今回はグループとチームの違いを比較することで強いチームづくりのヒントをお届けいたします。
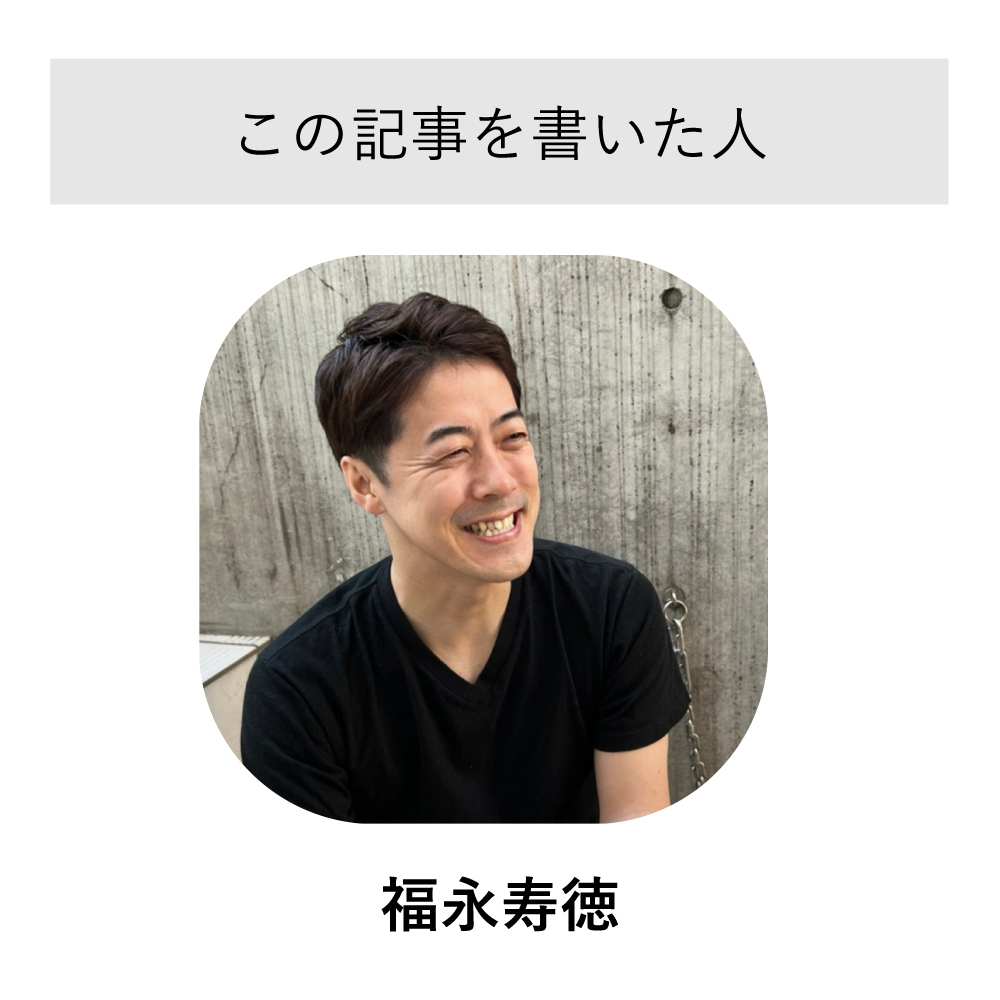
大学卒業後、ヘルスケア業界で1000名以上のトレーナーを育成。 セールス下手でも日本の隅々にまで展開することに成功。 好きで得意なことで役に立つと自分も周りも幸せだ。と確信する。 その後、独立起業。インナーブランディングの専門家として活動中。 趣味はトライアスロンだが走るのは嫌い。サウナとバスケ観戦が好き。 焼肉の部位はハラミ。フラップスプランの代表。
グループとチームの違いとは
グループとチームの違いってなんでしょうか?
例えばサッカーチームというのは存在するけど、サッカーグループはありません。仲良しグループはあるんだけど、仲良しチームというのは存在しない。
どうやら
グループ:共通項の人の集まり
チーム:1つの共通の目標に向かって共に協力をし合う集まり
という違いがありそうです。
サッカーチームは、日本代表から少年サッカーまでどんなレベルでやっていても共通している目標があります。それは「自分たちがより強くなり、相手に勝つこと」です。
もちろんレベルの違いは存在します。思いの強さと実力が単純に比例するわけでもありません。しかし、一つだけ確かなのは共通の目標を持ち、そのための努力を惜しまないからこそ、そのチームに所属する資格があるということです。
チームになるために大切なこと
では、そう考えたときに自分たちの会社はチームになれているでしょうか?
例えば、ある営業スタッフが当月売上目標を達成しなかった時。
A.上司から叱責されて、すぐにでもこんな会社辞めてやる!状態
B.「しょうがないよ」「よくあるよ」「気にしないで」と慰められて終わっている状態
C.上司から詰められて、胃は痛いけど次月こそは達成するぞ。と思っている状態
D.良くない行動について指摘をしてもらって、次月に生かそうという状態
みなさんのチームはいかがでしょうか?どこに当てはまりますか?
Aは負け犬グループです。心理的安全性も当事者意識・責任感もない状態。いつもビクビクしていなければならず、スタッフが早く仕事が終われと毎日思っているような会社です。
Bは仲良しグループの状態です。心理的安全性はあるけど、責任感がない状態。心地よいけど成果は出ません。
Cはキツいチームです。一昔前の軍隊のような会社です。それでも成果は出る分まだマシです。
Dは強いチームです。心理的安全性も当事者意識、責任感ともに高い状態。お互いに高めあうための指摘をし合える環境です。
強いチームだからこそできること
強いチームとはどういうことか。
それは「伝えるべきことをちゃんと伝える」関係性であること。
これができているから強いチームであるとも言えるし、これをしたから強いチームになったとも言えます。
私たちはついつい大人ぶった人間関係にしてしまいがちです。
例えば、その人が特に周りに迷惑をかけていなければ、わざわざもっとよくなることについての指摘はしません。なぜなら人間関係を悪くしたくないからです。わざわざ波風を立てる必要はない。と言いますが、実は単純に嫌われたくないからです。
まとめ
言いにくいことをちゃんと伝えること。
そして言われたほうは素直に一旦聞き入れること。
そのためには嫌われるかもしれないという恐れを手放して、相手のためを本当に想って発言するということがとても重要です。
日常から信頼関係を大切にしてお互いを高め合うための指摘を真っ直ぐすることで、強いチームを目指していきましょう!
強いチームを目指すために
強いチームをメンバー全員で目指すために、まず「強いチーム」の定義を揃えましょう!
ブログまたはこちらの動画を共有して、共通認識をつくることにご活用ください。
ワンネス経営®︎では定期的に、LINEやYoutubeを通じでチームビルディングのコツや、チームの生産性を向上させるポイントをお伝えしていきます。
チームづくりに課題を感じている方、是非ご確認下さい!
事務局:スズキヒラク
この記事を書いた人
![]()
福永寿徳
大学卒業後、ヘルスケア業界で1000名以上のトレーナーを育成。 セールス下手でも日本の隅々にまで展開することに成功。 好きで得意なことで役に立つと自分も周りも幸せだ。と確信する。 その後、独立起業。インナーブランディングの専門家として活動中。 趣味はトライアスロンだが走るのは嫌い。サウナとバスケ観戦が好き。 焼肉の部位はハラミ。フラップスプランの代表。
関連記事
-

2022.11.22
アダプティブラーニングの企業向けサービス・ツールおすすめ3選
チームづくり前回、アダプティブラーニングの概要についてお伝えしました。 アダプティブラーニングは教育現場で推進されていますが、企業の人材育成に活用することも可能です。 アダプティブラーニングを導入しようとする場合、「そもそもどのようなサービスやツールがあるのか」「自社に合ったものを探したい」と思っている方も多いかもしれません。 今回は、アダプティブラーニングの企業向けサービス・ツールのおすすめを厳選してご紹介します。 企業で活用できるアダプティブラーニングのサービス・ツール アダプティブラーニングは教育現場で広く採用されているため、システムやツールも基本的に教育機関用のものがほとんどで、企業向けに特化したものはそれほど多くありません。 ただし、教育機関用でもコンテンツを用意すれば利用可能だったり、日本企業に最適なシステムやツールも登場したりしており、少しずつ選べる範囲が広がってきています。 その中でも特におすすめなのが下記の3つになります。 Knewton Cerego Core Learn それぞれについて説明していきます。 Knewton 2008年に創立された「Knewton」は、アダプティブラーニングのパイオニア的存在です。 「学習者一人ひとりに最適な学習を」をスローガンに、世界中のトップクラスの教育関連企業や教育機関と数多く提携しており、東京にもオフィスがあります。 Knewtonでは、本人の目標や学習履歴、他の学習者の学習行動データ、人間の学習の仕組みに関する数十年にわたって行われた研究をもとに、独自のアダプティブラーニングシステムを提供しています。 このシステムの利用で、学習者が主体的に定めた目標の達成に向けて、それぞれの理解度や進捗度を把握し、一人ひとりにふさわしい学習ステップへと導くことができます。 教育全般に適用できるのはもちろん、さまざまな教科・科目や年齢層に対応できる柔軟性と拡張性が特徴です。 また、Knewtonは、アダプティブラーニング技術を実装した法人向けAPIプラットフォームを提供しています。 企業のパートナーは、自社のLMSやデジタルサービスとこのプラットフォームを接続することで、運営している学習サービス・コンテンツにアダプティブラーニングの導入が可能です。 参考:Knewton Cerego 「Cerego(セレゴ)」は、サンフランシスコに拠点を置くCerego社が開発したアダプティブラーニングのシステムです。 脳科学や認知心理学の研究結果など、学習科学の原理を利用した「記憶定着に特化した学習システム」という点が大きな特徴となっています。 エビングハウスの忘却曲線や分散型学習に、学習者それぞれのパフォーマンスを加えた独自アルゴリズムによって、記憶の定着と知識の蓄積が実現できます。 高度で豊富なアイテムテンプレートの中からコンテンツを作成でき、デザインやカスタマイズなどができるオーサリング環境も実装されているため、天文学から看護学まであらゆる学習コンテンツの構築が可能です。 また、学習者の進捗追跡、現状把握を含めた管理と計測がリアルタイムでできる他、あらゆるモバイルデバイスで、いつでもどこでもアクセスして学習ができます。 導入実績も増えてきている、今注目したいアダプティブラーニングシステムの一つです。 参考:Cerego Core Learn 「Core Learn(コア・ラーン)」は、印刷会社大手の凸版印刷が2017年に開発した、企業向けの完全習得型eラーニング・学習管理システムです。 学習者に合わせたスピードのeラーニングで業務に必要な知識を理解し、記憶に定着させることによって完全習得を目指します。 類題がランダムに出題されることで答えの丸暗記では解けないといった仕組みや忘却曲線理論に基づいた反復学習機能が、このシステムの特徴です。 企業が保有しているオリジナルコンテンツ(研修)のデジタル化はもちろん、「金融系」や「情報セキュリティ系」などプリセットコンテンツの利用も可能です。 当初は、金融機関向けに特化していましたが、現在では業種を問わずさまざまな企業に取り入れられ、100社以上の導入実績があります。 参考:企業向け完全習得型eラーニング「コア・ラーン」|TOPPAN EDUCATION まとめ 今回は、アダプティブラーニングの企業向けサービス・ツールのおすすめ3つを紹介しました。 実際に取り入れられそうなサービスやツールは見つかったでしょうか。 教育機関用のものが多いアダプティブラーニングのサービス・ツールですが、企業に活用できるものや企業に特化したものもあり、徐々に浸透してきています。 ぜひ、自社に合ったサービス・ツールを検討してアダプティブラーニングを導入し、人材育成に活用していきましょう。
-

2023.09.12
プロセスマネジメントの進め方と注意点について解説
チームづくり業務効率化や生産性アップを目的とし、「プロセスマネジメント」の導入を検討している方も多いのではないでしょうか。 この場合、具体的な実践手順や注意点を知っておくことで導入がスムーズに進みます。 今回の記事では、プロセスマネジメントの進め方と注意点を解説します。 「プロセスマネジメントを取り入れる手順を知りたい」という方は、ぜひ参考にしてみてください。 プロセスマネジメントの進め方 プロセスマネジメントを導入する場合、次の手順で進めるのがおすすめです。 業務プロセスを洗い出す 業務プロセスを可視化する プロセスを実行する プロセスを分析・改善する それぞれ解説します。 1.業務プロセスを洗い出す プロセスマネジメントを開始するにあたり、業務プロセスを詳細に把握することが必要です。 現場を実際に観察したり、担当者への聞き取りや議論を行ったりしながら、業務プロセスを洗い出していきます。 ただし、業務が特定の担当者に依存している場合、その業務内容は外部から理解しにくいことも多いものです。 このようなケースでは、継続的なコミュニケーションを取りながらプロセスを解明する必要があります。 2.業務プロセスを可視化する 次に、洗い出した業務プロセスを可視化していきます。 業務を可視化するには、「作業手順書」や「フローチャート」の作成が欠かせません。 この場合、誰でも業務内容が把握・実践できるよう、わかりやすくまとめるのがポイントです。 また、それぞれのプロセスごとに「目標値」を設定することも重要です。 目標を設定することで社員の意識向上につながるのはもちろん、生産性の確認・分析がしやすくなります。 負荷が大き過ぎない、無理のない範囲での目標値設定がおすすめです。 3.プロセスを実行する できあがった作業手順書やフローチャートを使って、プロセスを実行していきます。 業務の内容や作業手順が標準化されて明確になっているため、誰でもスムーズに進められるはずです。 特に、プロセスごとに設定した目標値を達成するよう心がけると良いです。 4.プロセスを分析・改善する プロセスマネジメントでは、定期的なプロセスの分析と改善を行う必要があります。 各プロセスでの目標達成度を含め、全体の生産性を確認することで、プロセスマネジメントの最適化が図れます。 また、分析によって明らかになった課題を解決するには、新たな業務プロセスを設計しなければいけないケースもあります。 例えば、業務の順番変更や不要な業務の廃止、工数が多い業務の自動化、といった方法の検討が必要です。 プロセスマネジメントで意識するべき3つの注意点 プロセスマネジメントを導入する場合、下記の3つの注意点を意識すると良いです。 時間がかかる 向いていない業務もある 負担が増える それぞれについて解説します。 時間がかかる プロセスマネジメントの実行にはある程度の時間がかかる点に、注意が必要です。 特に、初めて取り組む場合は、担当者に業務の詳細をヒアリングしたり、現場や使用ツールなどを調査したりするため、かなりの時間を要します。 そのため、事前に「プロセスマネジメントに時間をかける価値があるかどうか」という点についても考慮しておく必要があります。 向いていない業務もある プロセスマネジメントは、例えば、システム管理や検品作業、営業活動、総務人事など、パターンがある程度決まっている上、繰り返すことが多い業務に向いています。 一方、単発でしか行わないプロジェクトや、毎回業務プロセスが異なるような業務には向いていません。 プロセスを整理しても、作業の流れがある程度固定化されていなければ役に立ちにくいと言えます。 負担が増える プロセスマネジメントで重要なのは、実施後の分析・改善です。 プロセスごとに確認を行い、場合によっては効果検証を行わなくてはいけないため、管理職やマネジメント職の業務負担が増える可能性があります。 管理職・マネジメント職の負担を軽くするためには、業務管理ツールの活用などで業務効率化を図ることが重要です。 まとめ プロセスマネジメントを導入する際は、手順や注意点を把握しておくとスムーズに進められます。 進め方としては、「業務プロセスの洗い出し」、「可視化」、「実行」、「分析・改善」の手順で行うのがおすすめです。 また、時間がかかったり、向いていない業務があったり、負担が増えたりする点に注意が必要です。 ぜひ、今回の記事を参考にして、プロセスマネジメントを具体的に取り入れてみてください。
-

2022.10.11
リモート研修の課題点と研修の効果を高めるためのポイントを解説
チームづくりテレワークの普及によって、研修をリモートで行う機会も増えてきました。 リモート研修は通常の研修と異なる点があるため、「どのくらい理解されているのか」「質を上げる方法がわからない」といった悩みを抱えている方も多いかもしれません。 リモート研修の質を向上させるには、その特徴を理解して課題を把握しておくことが重要です。 本記事では、リモート研修について説明し、課題点と研修効果を高めるためのポイントを解説します。 リモート研修とは? リモート研修とは、オンライン上で行う研修のことです。 これまでの研修では集合して対面で実施する形が一般的でしたが、新型コロナウィルスの感染防止の観点やテレワークの普及によって、リモートで行う研修の導入が進んでいます。 テレワークと同様、リモート研修でもWeb会議システムやチャットツールなどを利用して行うため、従来の研修とあまり変わらない内容です。 また、「オンライン研修」という言葉もありますが、これらはほぼ同じ意味なので呼び方の違いになります。 メリット リモート研修を導入することのメリットとして、コロナウィルス感染のリスク低減はもちろん、手間やコストの削減も挙げられます。 従来の研修では、配布物を準備・配布したり、会場を手配したりと多くの手間がかかっていましたが、リモート研修なら必要最小限に押さえることが可能です。 また、交通費や会場代といったコストも削減できます。 さらに、リモート研修では一人ひとりの学習データが残るため、これを利用することで効率的に学習が進められます。 随時行われるフィードバックやコーチングで、反復学習や練習を能動的に行える点もメリットの一つです。 期待できる効果 リモート研修の実施で、従業員の自主性を高める効果が期待できます。 講師が一方的に講義を行う従来の研修とは異なり、リモート研修ではWeb会議システムで全員の顔を表示するため、相互に話しやすい環境です。 また、オンライン上のテキストや資料をいつでも見ることができるので、予習・復習などの積極的な学習姿勢を保てる効果もあります。 リモート研修の課題について それでは、リモート研修の課題にはどのようなものがあるでしょうか。 主な3つの課題点を下記に挙げてみます。 集中力が長続きしないコミュニケーションが不足するリモートに適した研修内容が必要 それぞれ詳しく説明します。 集中力が長続きしない 一人でパソコンに向かって受講するリモート研修では、周りに気を配る必要がないため、どうしても気が緩みがちです。 人の集中力は最大で約90分と言われていますが、リモート環境のもとでは90分間も集中が続きません。 15分周期の集中力の波を利用し、リモート研修の単位も15分にするなど、時間を工夫する必要があります。 コミュニケーションが不足する リモート研修では、受講者同士で雑談する場がほとんどありません。 オンラインで研修を受け、その後は課題に取り組む、といったスタイルでは、コミュニケーションが不足しがちです。 会社に溶け込みやすくすることも研修目的の一つと言えるため、気軽に話し合えるような全体設計が必要になります。 リモートに適した研修内容が必要 従来の研修では、座学だけでなく、受講生同士で話し合うといったグループワークなどの時間もとられています。 一方、リモート研修においては同時に話すことが難しく、活発なディスカッションを行うには人数を制限しなくてはなりません。 これまでと同じ研修内容では対応できない部分も多いため、リモートに適した内容にアレンジすることが重要です。 リモート研修の効果を高める3つのポイント では、リモート研修の効果を高めるにはどうしたらいいでしょうか。 ポイントとして下記の3つがあります。 講師とサポート役のタッグを作るできるだけ双方向のコミュニケーションを心がけるグループディスカッションは4人以下で行う 詳しく解説していきます。 講師とサポート役のタッグを作る 効果的にリモート研修を行うポイントとして、講師とサポート役のタッグを作ることが挙げられます。 講師には授業に集中してもらい、チャットツールなどの確認やシステムの不具合への対応をサポート役が行う、というように役割を分担することで、研修がスムーズに進みます。 リモート研修で起こりがちな問題をあらかじめマニュアル化しておくことも、おすすめの方法です。 できるだけ双方向のコミュニケーションを心がける 交流の機会が少ないリモート研修では、受講者同士、できるだけ双方向のコミュニケーションを心がける必要があります。 課題に対してのディスカッションやグループワークの時間を増やすなど、工夫をこらしたカリキュラムにするとうまくいきます。 また、チャットツールに雑談用ルームを作成することで、受講者同士で気軽な雑談が可能です。 グループディスカッションは4人以下で行う オンライン環境下では、人数が多いと、話すタイミングがつかめなかったり、会話をかぶせられなかったりしがちです。 大人数での話し合いは難しいため、ディスカッションは4人以下で行うことをおすすめします。 4人以下なら、お互いの顔を見ながら会話ができるので、話すタイミングをつかみやすいのはもちろん、全員が均等に話しやすくなります。 まとめ テレワークの普及によって、研修もオンラインで行うことが一般化してきました。 リモート研修にはメリットが多いですが、従来の研修とは異なる点もあるため、研修効果を高めるにはポイントをおさえておく必要があります。 リモート研修の質を向上させて、一歩上の人材育成を目指してみてはいかがでしょうか。
私が変わると、チームが変わる
ワンネス経営®プログラムは、インナーブランディング強化というアプローチを通して、 お客様企業が求める成果を達成していくという「新しいチームビルディングのプログラム」です。 イメージが持ちづらい点があるかもしれませんが、どうぞお気軽にご質問、ご相談ください。