Column
2022.04.12
インナーブランディングとは?目的とメリットを分かりやすく解説!
特集

目次
「社内を活気に溢れる状態にしたい」
「社員が定着するようにするにはどうすればいいのか?」
経営者や管理職にとっては、社内の士気を上げることや人材育成は課題の一つでしょう。
そんな課題の解決に役立つのがインナーブランディングです。
そもそもブランディングは、市場での自社の強み・ポジションを明確化することで、「○○といえばあの会社」というように浸透させていく活動を指します。
これは社外に対して行うことですが、インナーブランディングは、それを社内に向けたものです。
インナーブランディングを実施することで、社員の自社に対するイメージが向上し、企業活動が活発になるため、成果にも繋がります。
本記事では、「インナーブランディングとは何か?」について、その目的やメリットまで分かりやすく解説していきます。
インナーブランディングとは
インナーブランディングとは、企業理念やブランド価値を社員に伝えて浸透させる活動のことです。
社員一人ひとりが理解し、納得した上で意識変革をしていくことがインナーブランディングの核心といえます。
具体的な施策
インナーブランディングの具体的な施策は、以下のようなものが挙げられます。
- 社員研修
- 報酬制度
- 人事評価制度
などの教育活動のほか、具体的なシステム改革も含まれます。
インナーブランディングで価値観の共有が上手くできていると、社員一人ひとりが企業理念やブランドに愛着を持ち、仕事への向き合い方も変化します。
そして、目標達成のために「自分ごと」として企業活動に取り組むようになります。
「自分ごと」として仕事に向き合うとは、内発的動機付けを社員自らが感じて行動していることを意味します。
インナーブランディングでその環境作りをしていくことで、結果的に、商品やサービスの質が向上し、社員の業務効率アップなどに大きな効果をもたらすのです。
インナーブランディングの目的
インナーブランディングの目的は、企業理念やブランドに愛着を持てる社員を育成することです。
なぜなら、社員一人ひとりの言動や対応が、企業イメージに大きな影響を与えるからです。
たとえば、社員自身が自社に対して愛着がなければ、お客様に自社の商品やサービスを心からおすすめすることができません。それは、お客様側も敏感に感じ取ってしまいます。
社員一人ひとりの企業理念やブランドコンセプトに基づいた行動により、企業理念の実現やブランド価値の体現につながるのです。
インナーブランディングのメリット3つ
インナーブランディングに取り組むメリットは、社員の満足度の向上や連帯感の強化、離職率の軽減など数多くあります。
こちらでは、メリットを3つに絞り解説していきます。
インナーブランディング 3つのメリット
- 組織のパフォーマンスの向上
- ロイヤリティの向上
- 社員の定着率が上がる
それぞれのメリットを以下で詳しく解説します。
組織のパフォーマンスの向上
インナーブランディングには、組織のパフォーマンスが向上するというメリットがあります。
なぜなら、企業理念やブランド価値について社員の理解を深めることが、自社に対するイメージが上がり、社員同士の連帯感強化にもつながるからです。
社員全員がメンバーの一員であるという思いで社員が互いに助け合い、組織全体の生産性が高まる効果が期待できます。
ロイヤリティの向上
インナーブランディングを実施することで、社員のロイヤリティが高まります。
この場合のロイヤリティとは、社員が勤める企業に対して抱く、「信頼」や「愛着」「帰属意識」のことを指します。
つまり、インナーブランディングは、企業と社員の信頼関係の強化につながるのです。
社員の定着率が上がる
インナーブランディングで社員が勤める企業に対する信頼度や好感度が高まるため、人材の定着や確保にも大きく貢献します。
また、自社の価値を正しく伝えられることで、自社に合う優秀な人材も採用しやすくなります。
強力な企業理念や価値観は多くのファンを生み、「チームに参加したい」という強いモチベーションを持った人材が集まります。
企業が掲げる理念や価値観に合う人材が集まるため、ミスマッチを防ぐことができ、早期離職防止にもなるため、採用コスト削減にも効果的です。
まとめ
今回は、インナーブランディングについて解説しました。
社外に向けて行ういわゆるブランディングも大切ですが、社員に向けて行うインナーブランディングもとても重要です。
社員が自社の理念についてよく知らなかったり、待遇に対して不満を抱いたりしているままでは、社内の士気も落ちてしまいますし、何より顧客に対して質の高いサービスすることはできません。
インナーブランディングを成功させることは、決して簡単なことではありません。
しかし、インナーブランディングが成功すれば、企業にとって大きな利益をもたらすのです。
インナーブランディングの強化を通じて、業績の向上に貢献するワンネス経営®︎
ワンネス経営®では公式LINEやYoutubeチャンネルでチームづくりのコツやコミュニケーションのポイントをお伝えしています。
具体的な行動方法まで詳しくお伝えしているため、知らなかった状態から→知っていて学びを活かせる状態になる事が可能です!
職場のコミュニケーションのズレを解消し、チームの生産性が上がると結果として売上も上がっていきます!
事務局:スズキヒラク
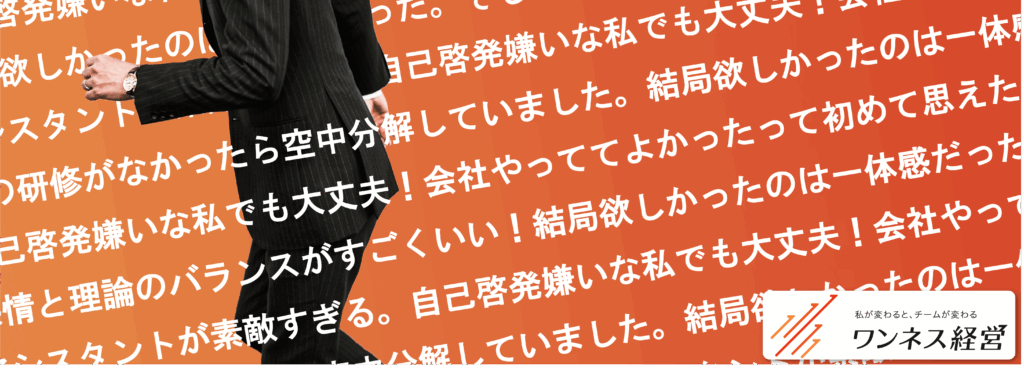
この記事を書いた人
![]()
永井 祐子
愛知県出身 Webライター。「やってみなきゃ分からない!」がモットー。持ち前のチャレンジ精神と思い切りのよさを発揮し、 OLから憧れだったライターの世界へ飛び込む。ライター業をする中でコンテンツマーケティングの奥深さに魅せられ、極めるために日々研鑽中。趣味は、映画を観ること、一人旅。好きな名古屋めしは、味噌串カツ。
関連記事
-

2025.09.09
トラブルでも止まらない思考法
特集ついに、今週の日曜日、9月14日にIRONMANです! 出場しない僕も何故かソワソワ! 何故なら社長が8月中旬にふくらはぎを肉離れしてしまったからです。 日々のトレーニングを行う中で、気づかないうちに疲労が溜まっていたそうです。 本日は、思いもよらぬトラブルに直面しても挑戦をやめない社長の姿勢から「逆境でも前に進むためのヒント」をお届けします! 悩まない!落ち込まない!すぐ行動! レース4週間前のとある日。 ふくらはぎを痛めた時に、私は近くに一緒にいました。 社長は、肉離れを何回か経験者、且つ元理学療法士です。 なので、すぐに「これは軽度じゃない」と理解して、お知り合いの方に相談し“MRIが取れる整形外科に行く”とすぐに向かいました。 3時間後には松葉杖で帰ってきていました。 この行動を見て、くよくよしていても現実は変わらない。 現実を変えられるのは、行動だけ。行動を変えれば、感情も変わる。と気づかせていただきました。 この視点は、ビジネスでも同じです。 どんなトラブルや不足の事態も「まず動く」ことでしか乗り越えられません。 捉え方を変える 生活しているとマイナスに捉えてしまうことってありますよね。 例えば今回のケースなら、肉離れをして「終わった。もう走れない。諦めよう。」と捉えるのか、「ヒーローになるチャンスが来た。人生で語れるネタが始まった!」と捉えるのかで、行動はまったく変わります。 どちらを選びますか? 捉え方1つで印象が変わります。 もちろん反省は、大切です。 でも、落ち込みながら反省することと、前向きな気持ちで反省するのではどちらの方が良いでしょうか。 同じ出来事でも「マイナス」に捉えるか「チャンス」と捉えるかで、その後の成果はまったく変わってきます。 これは経営や組織づくりにも通じる考え方ですよね。 これは日頃からの訓練が必要になってくると思います。 フラップスでは「キラキラ上機嫌」という表現をしています。 これは、態度は選べるということです。 自分で良い面を見るのか、悪い面を見るのか決められるということです。 平時からの心のトレーニングが、いざという時に力を発揮するのだと感じました。 ちなみに私は、落ち込んだ時は、すぐに感情などを可視化して、前向きな捉え方の文章を脳内で唱えています。笑 頼る力と優先順位で目標を達成する 研修も仕事もトレーニングもあり、焦りや不安もあった中で、社長は食事(栄養)と睡眠を工夫しました。 フラップスには、ハイパー管理栄養士の優生さんがいます。 すぐに相談し、必要な栄養素を取り入れ、成長ホルモンを活かすために睡眠時間の確保ができるように努めていらっしゃいました。 正しい知識と工夫が、目標に着実に近づく力になるのだと実感しました。 そして、ここで一番感じたのは「頼ることの大切さ」です。 自分でやるんだ。というプライドより、目標を達成するんだという責任感の方が大事だと感じました。 みなさんは、何か挑戦するとき、つい1人で抱え込んでいませんか? 専門家の力を借りることで、的確な情報が手に入り、目標への最短ルートを進むことができます。 これはスポーツだけでなく、ビジネスや日常生活の挑戦にも通じる学びだと思いました。 まとめ 肉離れをした日。 実は、その日とても落ち込んでいたそうです。 しかし、無理にでも切り替えて行動に移していたと、後日聞きました。 どんな出来事も「どう捉えるか」でその後の行動や成果は大きく変わります。 そこで特に意識したい3つのポイントは次の通りです。 ・まず行動すること・捉え方を前向きにすること・優先順位を決めて集中すること これらの姿勢こそ、結果を出すために大切だと思いました。 IRONMAMまで残り5日! ぜひ社長の挑戦を見守ってください!
-

2021.07.22
最高のチームの作り方 大嶋啓介 氏
特集今回はよりよいチームづくりの方法を学ぶため、 組織の可能性を引き出すスペシャリストとして有名な株式会社てっぺん創業者の大嶋啓介さんをお迎えしました。 「最高のチームのつくり方」 についてインタビューをさせていただきましたのでご覧ください! 是非ご自身のチームづくりに生かしていってください! 大嶋啓介さんのプロフィール 大嶋啓介(おおしまけいすけ)氏◯株式会社てっぺん 創業者◯NPO法人居酒屋甲子園 初代理事長 ■著書 ◯『予祝のススメ 前祝いの法則』(共著:ひすいこたろう氏)◯『すごい朝礼 たった15分で人生が変わる』 2004年、居酒屋から日本を元気にすることを目的に居酒屋「てっぺん」を設立。2007年には外食産業に最も影響を与えた人に贈られる「外食アワード」を受賞した。「日本中に夢を広めたい」という熱い念いから、企業・学校・部活動へと活動の場を広げ、「夢を大切にする生き方」「人を惹きつける魅力的なリーダーの在り方」などのテーマで全国各地で講演を行っており、2018年6月に出版した「予祝のススメ 前祝いの法則」は7万部を突破! ▷大嶋啓介オフィシャルHP チームづくりのポイント1「目標が楽しいかどうか」 インタビュアー:経営者の悩みとして、「経営陣だけが燃えているけど、社員の元気がない。ついてきてくれない。」ということがあるのですが、大嶋さん流の生き生きとしたチームづくりのポイントを教えてください! 大嶋さん:会社でもお店でも、何にしても“目標がおもしろいかどうか”がすごく大事だと思っています。 自分自身もお店の店長をしていた時やてっぺんの会社経営の時には、 みんながワクワク楽しめるような目標だったり、みんなが楽しめるようなビジョンだったりを すごく大切にしていました。 「社員にやる気がない」というのは、社員が悪いのではなくて、目標がつまらないからで。 仕事にやりがいを持たせる方法はいくらでもあります。 やり方よりも「全員でこの職場を楽しくする」とか「全員でこの仕事をやりがいのあるものにしていく」とか そういう意識を作ることが一番大事だと思います。 働く場所は変えられなかったとしても、どんな仕事でも、どんな職場でも楽しんで働くことはできるんです。 大切なことはやっぱり“楽しい”なんですよね。 働く職場が楽しくてやりがいのあるものじゃないと続かないので。 会社経営者の方からしたら「いやいや飲食はすこし特殊でしょ」とか「目標を楽しくするって言われてもイマイチよく分からないよ」って方も多いと思います。 私がもし飲食以外の業界の会社を経営することになったら、まずは日本中で「働く人がやりがいを持って、生き生きしている同業の会社」ベスト5を探します。 そしてそこでは「どんなチームづくりをしているのか?」「どんな取り組みをしているのか?」「なんでそんなに社員が楽しそうなのか?」 をものすごく学んで、自分のチームにどんどん取り入れるっていうことをやりたいですね。 チームづくりのポイント2「社員育成は出番を作る」 インタビュアー:チームづくりにおいて男性、女性の違いで気をつけたり、意識されていることはありますか? 大嶋さん:基本的にはスタッフに任せてしまうことが多いですね。 あんまり男性女性という分け方はしないですけど、チームの中で女性リーダーをつくって、その人に任せるということはよくやります。 とにかくその女性リーダーとたくさんコミュニケーションをとって、その人には自分の言いたいことが何でも言えるという関係性を作ります。 自分が店長だった時も女性のリーダーをつくって、その人の育成をしっかりやってました。 全員に対してももちろん関わるんですけど、その女性リーダーに任せることの方が多かったり、スタッフからの相談ごとも集まるようにしたり、 なるべくその人の出番をつくるようにしていました。 男性でも女性でもうまくスタッフの出番をつくってあげることが大事だと思いますね。 チームづくりのポイント3「コミュニケーションでチームづくり」 インタビュアー:職場の雰囲気を変えたい!と思っているリーダーに向けて大嶋さんからアドバイスをするとしたらどんなことをされますか? 大嶋さん:先ほども言いましたが、私が職場を変えたいと思ったら、 まずはみんなで学びに行ったりして、何かきっかけをつくります。 例えば、私がいきなり社長をやることになって、 周りからの信頼もない、自分の技術も自信もない、 そんな状態からチームをつくっていくとしたら、 いきなり「こう変えよう!」というんじゃなく、 みんなと「どんな職場だったら楽しいか?」「どんな仕事だったらやりがいを感じるか?」というアイディア出しを一緒にして、 自分の考えと合わせながら「みんなでこうしたい!」と思える方向を決めていきますね。 自分自身いろいろなお店の店長を経験した中で、 ほんとにコミュニケーションを通してチームづくりをしてました。 やっぱりみんなと一緒に成長していきたいし、人が成長できる環境ややりがいを見つけていくことを大切にしたかったので。 チームづくりのポイント4「楽しさの追求が最強」 大嶋さん:とにかくチームづくりに欠かせないものは『楽しさの追求』です。 楽しいの追求は本当に最強です。 経営者の仕事は「いかに社員さんを楽しませてあげるか」 楽しいといってもいろいろな楽しさがあるので、 「みんなは何に楽しさを感じるのか?」 ということを大切にしていきたいですね。 楽しいことをたくさんやる。 極端な話「毎月社員旅行に行く」とか。 1年間くらい利益は全部社員さんに還元して、とにかく育成と楽しさに投資します。 もちろんただ楽しいだけじゃなくて、楽しさの中にチームづくりの要素を入れていきながらですけど。 私が職場を変えようと思ったらそのくらいやりますね。 チームづくりのポイント5「職場が楽しくなる100項目」 インタビュアー:最後に明日から実践できるような行動のポイントがあれば教えてください。 大嶋さん:「職場が楽しくなる方法を100個考える」 とにかく楽しさを追求して、どうやったら今より1ミリでも職場が楽しくなるか? というアイディア出しをする。 一人でやるのもいいんですが、できれば幹部と一緒にやるといいと思います。 そのリストの中からできることを実践していく。 「今月はこの3つをやろう」とか「今週はまずこれをやってみよう」とか とにかく「楽しさの追求」これに尽きると思います。 インタビュアー:ありがとうございました! まとめ お話を伺って感じたのは、 インナーブランディング強化のヒントとなることばかりだということ。 ご本人はインナーブランディングについての意識はありませんが、 結果として、大嶋さんのお話は私たちフラップスプランが伝えたいことともリンクしていてとても勇気をいただきました! とにかくチーム作りで大切なことは『楽しさの追求』 ・働く社員が楽しく生き生きしている同業の会社さんTOP5 ・職場を楽しくするための社員へのヒアリング、 ・100個のアイディア出しなど、 すぐに実践できるヒントがたくさんあったと思います。 何か1つでもご自身のチームに取り入れることで変化を起こしましょう。 ぜひ、素晴らしいチームづくりにご活用ください。 これからも、私たちはもっとたのしくおもしろく働く人を増やして、 生き生きと成果を出すチームを日本中に増えることを応援していきます! さらに最高なチームづくりを行うために! マネジメントやチームづくりについてワンネス経営®︎では登録者限定に即活用できるお役立ち情報を配信しています。 目標達成や時間管理、チームの生産性を向上させる為のヒントが満載です! メンバーに仕事を楽しみながら成果を出してもらうコツは何か?主体的に取り組んでもらう為のポイントはどんなものか?などお悩みの経営者・管理職の皆さん是非ご登録下さい! 事務局:スズキヒラク ワンネス経営®︎公式LINEを追加!
-

2022.04.19
インナーブランディング実践編|施策の3ステップと企業の成功事例3選
特集今回は、インナーブランディングの実践編として、インナーブランディングの活用方法を3ステップで解説し、企業の成功事例をご紹介していきます。 本記事を読むことで、具体的な実践の方法が分かり、インナーブランディングにより他の企業はどのように成功できたかを知ることができます。きっと自社の人材育成にとってのヒントが見つかるはずです。 インナーブランディングを成功させるための3ステップ 実際に、インナーブランディングを進める手順は、大きく分けて3ステップになります。 ミッション・ビジョン・バリュー(MVV)の策定社員への理念浸透フィードバック(効果計測) それぞれ以下で詳しく解説します。 ミッション・ビジョン・バリュー(MVV)の策定 ミッション・ビジョン・バリュー(MVV)とは、企業の目指す姿、果たすべき使命、大切にしている価値観などを表したものです。 MVVとは ・ミッション(Mission)=企業が果たす使命・社会における存在意義 ・ビジョン(Vision) =企業が目指す未来の姿 ・バリュー(Values) =行動・判断の基準となる企業の価値観 これらを明確に定めることにより、社員一人ひとりが「この会社で働く意味はなにか」「自分が勤める企業はどんな目標に向かっているのか」「今どんな判断をしてどのような行動をすべきか」を意識できるようになります。 社員への理念浸透 インナーブランディングの成功のカギは、社員への理念浸透ができているかにかかっています。 具体的には、 社内報社内チャットクレド(行動指針)社内イベント研修やセミナー日報 など、理念浸透のための伝達の手段は様々です。 それぞれの手法については、こちらの記事をご覧ください。 https://flapsplan.co.jp/blog0006/ フィードバック(効果計測) インナーブランディングは短期間で成果があがるものではありません。 そのため、定期的にフィードバックとして効果測定を行うことが重要です。 調査手法として定量的調査と定性的調査があります。 定量的調査では、社員アンケートが一般的で、客観的な視点での設問や分析が有効であるため、社外に依頼するケースが多いです。 定性的調査は、グループインタビューが挙げられます。複数人のグループを作り、特定のテーマについて議論してもらいます。 これらのフィードバックで、改善点を見つけ出しPDCAサイクルを回していきます。 企業の成功事例 実際にインナーブランディングを導入し、成功した企業の事例をご紹介していきます。 スターバックスコーヒーの事例 インナーブランディングの成功事例として、有名なのが、「スターバックスコーヒー」です。 スターバックスコーヒーでは、広告に費用をかけるかわりに、人材育成に費用と時間をかけることでホスピタリティの向上に成功しています。 接客レベルの高さを築いているのは、マニュアルではなく、全てスターバックスで働くパートナーの自主性によるものなのです。 なぜ、自発的に質の高い接客を提供できるのでしょうか。 それは、充実した研修制度により、スターバックスコーヒーの企業理念・行動規範がパートナーに浸透しているからです。 研修の中で理念や行動規範について細かく触れる機会があるため、現場で働くパートナーは「お客様に心地よい接客体験」を提供するにはどうすればいいのか、と考えながら働くことができるのです。 その結果、スターバックスコーヒーは広告費をかけずに、パートナーの質の高い接客や「サードプレイス」としての環境がブランドとして確立し、多くの人々に愛されるカフェになっています。 サイバーエージェントの事例 サイバーエージェントでは、マネジメント・カンファレンスを取り入れた「あした会議」を開催しています。 「あした会議」は、役員がチームリーダーとなり社員とチームを組んで、サイバーエージェントの「あした」をつくる新規事業や課題解決を提案する1泊2日の合宿です。 「あした会議」は、サイバーエージェントの中でも事業創出、課題解決の手段として大きく機能しており、あした会議により決まった子会社28社から生まれた売上は累計700億円にのぼっています。 この取り組みにより、社員は社長はじめ役員の視点を学ぶことができ、部署を超えて社内情報の共有ができるため、会社を取り巻く状況についての理解を深めることができます。 また、主催する経営層にとっては優秀な人材をより成長させる場としても活用されています。 リッツ・カールトンの事例 リッツ・カールトンは、お客様の要望に応える心のこもったサービスを提供することを理念に設立された世界規模でチェーン展開しているホテルブランドです。 リッツ・カールトンのサービスに対する考え方は、 クレドサービスの3ステップモットーサービスバリューズ従業員への約束 からなるゴールド・スタンダードに集約されています。 リッツ・カールトンといえば「クレド」が有名ですが、世界中の従業員が常にゴールド・スタンダードが書かれた「クレド・カード」を携帯しています。 これは、リッツ・カールトンで働くホテルマンとしての誇りの表れともいえるでしょう。 これにより、従業員が「最高のサービスとは何か」を自分ごととして考えるようになることが、結果としてリッツ・カールトンらしさを作り出し、顧客の期待を超える感動のサービスを提供し続けているのです。 まとめ インナーブランディングの活用方法と企業の成功事例についてお伝えしました。 インナーブランディングは一朝一夕にできるものではありません。 しかし、今回成功事例でご紹介した企業は、社会において唯一無二の存在感を示しています。 これはつまり、インナーブランディングにより社員一人ひとりに理念浸透できることで、組織の駒ではなく企業の価値基準に基づく社員の自発的な仕事ぶりが、結果的にブランディングにつながる証左といえるでしょう。 インナーブランディングを強化することで業績の向上に貢献する インナーブランディングの強化を通じて、業績の向上に貢献するワンネス経営®︎プログラムを提供しています。 ・人材育成で課題を抱えている・個人と組織の生産性を向上させたい・社内で共通の言語、共通の価値観を持って仕事に取り組んでもらいたい など、お悩みをお持ちの経営者の方、どんな些細な事でもご相談ください! 事務局:スズキヒラク ワンネス経営®︎プログラムの内容はこちらから!
私が変わると、チームが変わる
ワンネス経営®プログラムは、インナーブランディング強化というアプローチを通して、 お客様企業が求める成果を達成していくという「新しいチームビルディングのプログラム」です。 イメージが持ちづらい点があるかもしれませんが、どうぞお気軽にご質問、ご相談ください。

