Column
2022.12.13
コンプライアンス研修の準備方法|実施までの流れをわかりやすく解説!
チームづくり

「コンプライアンス研修をやることになったけど、まず何からしたらいいのだろうか」と悩んでいる方も多いかもしれません。
研修をスムーズに進めるためには、あらかじめしっかり準備をしておくことが重要です。
コンプライアンス研修を実施する場合、どのような準備が必要なのでしょうか。
今回は、コンプライアンス研修を実施するまでの準備について、その流れをわかりやすく解説します。
コンプライアンス研修の準備の流れ
コンプライアンス研修を準備する際の流れは下記の通りです。
- 研修の目的を決める
- テーマ・内容を決める
- 対象者を決める
- 研修形式を決める
それぞれの段階で行うことについて説明します。
研修の目的を決める
はじめに、コンプライアンス研修を行う目的を明確にしておきましょう。
目的が曖昧なまま準備を進めてしてしまうと、この後に決めるテーマや内容のポイントがブレてしまいます。
前回の記事でも紹介しましたが、研修の目的には主に下記の3つがあります。
- コンプライアンス知識の理解
- コンプライアンス違反へのリスクヘッジ
- 企業の価値向上
新入社員に基本的なルールを教えるためなのか、コンプライアンス違反が起こった後の対応を教えるためなのか、といった実施目的を定めておくことが重要です。
テーマ・内容を決める
目的を明確にしたら、研修のテーマと内容を決めていきます。
テーマを決める時のポイントとして、さまざまなコンプライアンス違反の事例を参考にすることが挙げられます。
その際は、事例を紹介するだけでなく、実際の業務の際に起こり得るコンプライアンス違反を研修に反映させると良いです。
また、社会的に話題性のあるテーマを取り上げれば、研修に対して興味・関心を持ちやすくなります。
そして研修内容を決める時は、業務や分野ごとにまとめながら行うのがおすすめです。
研修資料も、情報をまとめるように意識して作成すれば、受講者の予習や復習に大いに役立ちます。
対象者を決める
次に、研修テーマごとの受講対象者を決めます。
同じテーマの研修を全社員が受ける必要はありません。
経歴や役職、業務内容によって最適な研修は異なるため、テーマごとに受講すべき社員カテゴリーを選択します。
例えば、コンプライアンスの基本や社会のルールがテーマなら新入社員を対象に、またコンプライアンス違反が起きた時の対処法などがテーマなら管理職を対象にするといった具合です。
研修形式を決める
テーマと内容が決まったら、研修の形式を決めていきます。
コンプライアンス研修の形式には、以下の4つがあります。
- 社内で行う
- 講師を呼んで行う
- オンラインで行う
- 社外研修への参加
それぞれについて説明します。
社内で行う
コンプライアンス研修の一般的な形式として、社内での集合研修があります。
ほとんどの場合、総務や人事の担当者が講師として行うことになり、内容を練ったり、資料を作成したりなどの入念な準備が必要です。
担当者に大きな負担がかかる一方、コストや受講者の手間がかからないといったメリットもあります。
また、社内での集合研修は説明だけのインプット型になりがちですが、アウトプットを適度に取り入れるとスムーズな知識習得が可能になります。
特におすすめなのが、少人数グループで行う、コンプライアンスをテーマとしたディスカッションです。
こういった時間を取り入れることで、研修が活発化するのはもちろん、社員同士のコミュニケーションも図れます。
講師を呼んで行う
社内でコンプライアンス研修を実施する場合、専門の講師を呼んで行う形式もあります。
リスクマネジメントに精通した専門家や弁護士などに研修を行ってもらうことで、具体的な経験に基づいたより深い知識が身につきます。
研修全体ではなく、一部の時間を使って話してもらうのもおすすめです。
コストはかかりますが、新鮮かつメリハリのある研修を目指すなら検討の余地があります。
オンラインで行う
オンラインで行うことで、場所や時間を問わずにコンプライアンス研修の実施が可能です。
リモートワークが定着した現在では、オンライン研修やeラーニング研修も一般的になっています。
コンプライアンス研修が可能なシステムやツールを上手に選んで活用すると良いです。
社外研修への参加
社外で開催されている研修やセミナーに参加する形式もあります。
社外の人たちとの交流が図れたり、一般的な常識を得やすかったりといったメリットがある反面、自社や担当業務への活用が難しいといったデメリットもあります。
社外でのコンプライアンス研修に参加する際は、活用可能な内容なのかしっかり検討することが大切です。
まとめ
コンプライアンス研修を準備する際は、目的を明確にしてからテーマ・内容を決め、対象社員と研修形式を決めていくという流れになります。
コンプライアンス研修にはさまざまなテーマや内容があるため、はじめに行う「目的の明確化」が最も重要と言えます。
最後に決めるべき研修形式も、自社に合ったものを選択すると良いでしょう。
何を準備すればいいのか迷っている方は、ぜひ今回の記事を参考にしてみてください。

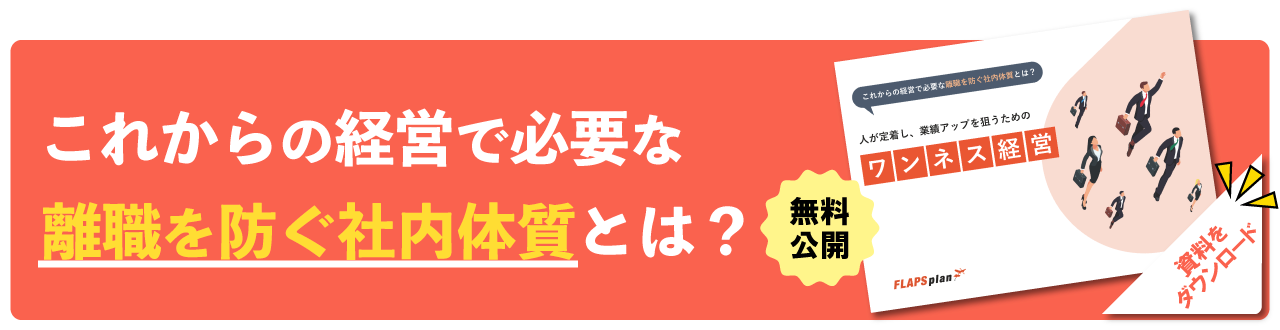
この記事を書いた人
![]()
泉水 ちか
東京都在住のWEBライター。フリーランスで様々なジャンルのライティングをこなす。人のこころに興味があり、心理学・カウンセリングの資格を多数取得。マーケティングにも活かすべく奮闘中。趣味は映画鑑賞(ホラーやアクション!)と温泉・銭湯めぐり。長年、放送業界にいたため音楽に詳しい。運動嫌いのインドア派だが夏フェスは好き。ラーメンと寿司と焼肉があれば大丈夫。
関連記事
-

2023.08.29
プロセスマネジメントとは?注目されている背景やメリットを解説
チームづくり近年、プロセスを重視するマネジメント手法である「プロセスマネジメント」が注目されています。 プロセスマネジメントを取り入れることで業務効率化や生産性向上に効果があるとされ、業務の成果を最大化できます。 今回は、プロセスマネジメントについて、注目されている背景やメリットを解説します。 プロセスマネジメントについて詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。 プロセスマネジメントの概要 プロセスマネジメントとは、業務の結果ではなく、「プロセス」を分析し管理するマネジメント手法のことです。 業務の結果はその過程(プロセス)から生み出されるため、過程を最適化することで成果も最大化させる、という考えがベースになっています。 例えば、営業部のメンバーをマネジメントする場合、契約数などの結果にだけ注目してしまうと、どのような過程を経て、そこに至ったのかが不明のままです。 プロセスがわからないままでは、適切な改善策も見つかりません。 一方、プロセスマネジメントでは、営業の業務内容を「商談」、「見積り」、「契約締結」といった細かい段階に分解し、それぞれにおいての良し悪しを判断します。 各業務プロセスでの問題点が明確になるため、改善策が見つけやすくなります。 注目されている背景とは プロセスマネジメントが注目されている背景として、業務効率化や生産性向上の必要性が挙げられます。 日本は他国に比べて生産性が低いとの課題があり、公益財団法人日本生産性本部が調査した「労働生産性の国際比較 2022」でも27位という結果です。 また、今後の人口減少も相まって、労働力の確保と競争力の向上が企業の重要な焦点とされており、業務効率化や生産性向上がこれまで以上に重要視されています。 そのため、営業職などの業務においても業務プロセスを最適化する必要性が高まっているのです。 参考:労働生産性の国際比較2022|公益財団法人 日本生産性本部 プロセスマネジメントのメリット プロセスマネジメントには、主に下記の4つのメリットがあります。 プロセスを可視化できる 業務の進捗状況を把握しやすい 業務の属人化が防げる ミスやトラブルが防げる それぞれ解説します。 プロセスを可視化できる プロセスマネジメントの大きなメリットとして、プロセスの可視化が挙げられます。 プロセスマネジメントでは、プロセスごとにフローチャートや手順書などの作成が必要なため、携わるメンバー全員での把握・共有が可能です。 プロセスを可視化して共有すれば、チームの共通認識ができ、メンバー間での連携がスムーズになります。 業務の進捗状況を把握しやすい プロセスマネジメントでは、プロセスごとに業務を管理します。 そのため、個々のプロセスの進捗状況が把握しやすい点がメリットです。 進捗状況の把握によって、各業務にかかっている時間が明確になることで、改善ポイントの発見につながります。 また、リアルタイムで進捗状況を把握することで、計画と現状を比較しながら業務全体の進捗管理を行うことが可能です。 業務の属人化が防げる 業務の属人化が防げることも、メリットの一つです。 業務が属人化している場合、その担当者が不在時に業務が停滞したり、退職してノウハウが失われたりしてしまうおそれがあります。 さらに、業務が集中することで長時間労働が発生する可能性も高いです。 業務の棚卸しやフローチャートの作成などプロセスマネジメントを行えば、それぞれの業務プロセスが明確になり、業務の属人化を解消できます。 ミスやトラブルが防げる プロセスマネジメントを取り入れると、ミスやトラブルの防止にもつながります。 例えば、業務担当が属人化されている場合、他の誰もミスやトラブルに気づかなかった、といったケースが起こりがちではないでしょうか。 プロセスマネジメントで業務フローの型化ができていれば、ミスやトラブルの原因特定や今後の課題が明確化しやすくなります。 まとめ プロセスマネジメントは、結果ではなく、そのプロセスに焦点を当てることで成果の最大化を図るマネジメント手法です。 業務効率化や生産性向上の必要性を背景として注目されており、プロセスの可視化ができ、業務の属人化を防げるといったメリットがあります。 今回の記事を参考に、プロセスマネジメントについて理解を深め、導入を検討してみてはいかがでしょうか。
-

2025.05.20
人間力を高めるには?日常で取り入れやすい具体的な3つの方法も紹介!
チームづくり人間力が高い人は、ビジネスでも日常生活でも信頼され、周囲と良好な関係を築きながら活躍しています。 しかし、人間力を高めるにはどのようにしたらいいかわからないという方も多いのではないでしょうか。 そこで本記事では、人間力を高めるにはどうしたらいいのか、その概要を解説し、日常で取り入れられる具体的な3つの方法を紹介します。 ぜひ、参考にしてみてください。 人間力を高めるには 人間力とは、スキルや資格といった表面的な能力ではなく、より深い人格や器量に関わる総合的な力です。 人間力を高めるためには、自分自身を「当事者」と捉え、責任感を持って行動する主体性が基盤となります。 刺激にすぐに反応するのではなく、一度立ち止まって選択する習慣を身につけることで、この主体性は育まれていくものです。 また、将来の自分像を明確にし、「どのような人間になりたいか」という問いに向き合うことで、日々の決断や行動に一貫性が生まれ、周囲からの信頼を得やすくなります。 視野を広げてさまざまな見方を知ることで思考の幅が広がり、他者への理解や尊重にもつながります。 さらに、日常の中で目的意識を持ち、一日の終わりに自分の行動を振り返る習慣も大切です。 人間関係においては、相手への敬意と理解の姿勢が欠かせません。 互いを尊重し合い、相手の立場や考えを理解しようと努めることで、スムーズなコミュニケーションが可能になります。 これらのポイントは日々の積み重ねによって習慣となり、やがて人間性として定着していきます。 人間力を高めるとは、日々の小さな選択と行動の中で、より良い自分を目指す継続的な取り組みなのです。 人間力を高める具体的な方法 それでは、人間力を日常で高めていくには、どのようにすればよいのでしょうか。 人間力を高める具体的な方法として挙げられるのは、次の3点です。 理想の姿を意識して行動する 他者への思いやりを持つ 知識をアップデートする それぞれ解説します。 理想の姿を意識して行動する 「なりたい自分」を明確に描くことが、人間力向上の第一歩です。 具体的な理想像を持つことで、日々の選択や行動に一貫性が生まれます。 この理想像は、歴史上の偉人でも、身近な尊敬する人でもよいです。 理想像を持つことは、模倣ではなく、自分自身の軸を育てる過程でもあります。 「この状況で、あの人ならどう判断するだろう」と自問することで、理想に近づく選択ができるようになります。 特に困難な場面では、怒りや焦りに任せる前に、一瞬立ち止まって理想像を思い浮かべることが重要です。 他者への思いやりを持つ 人間力の本質は、自分と他者との関係性の中にあります。 私たちは常に誰かの助けを借り、誰かに影響を与えながら日々を過ごしています。 この相互依存の関係の中で、思いやりの心を持つことは、人間社会で生きていくための大事なポイントです。 職場では、役職や立場に関わらず、一人ひとりを個性ある人間として尊重する姿勢が必要です。 意見の衝突があったときこそ、相手を非難する前に「自分に改善点はなかったか」と内省する習慣が、人間としての深みを生み出します。 また、日常のあらゆる場面で「ありがとう」と感謝の気持ちを表現することも、人間力を高める大切な習慣です。 知識をアップデートする 常に学び続ける姿勢も、人間力の重要な側面です。 現代社会は急速に変化し、昨日の常識が今日は通用しないこともあります。 ちょっとした疑問に「なぜだろう」と立ち止まって調べてみる習慣や、新しい情報に触れればすぐに意味を確認する好奇心、こうした小さな行動の積み重ねが、知的な柔軟性を生み出します。 特に効果的なのが、得た知識を誰かに説明してみることです。 人に伝えるために情報を整理し言語化する過程で、知識は確実に自分のものになります。 また、一日の終わりに「今日の出来事から何を学んだか」と振り返る時間を持つことで、経験が将来に活かしやすくなります。 まとめ 人間力の向上は一朝一夕では達成できませんが、「理想の姿を意識する」「他者への思いやりを持つ」「知識を常にアップデートする」という3つの実践から始められます。 これらを日々の小さな習慣として積み重ねることで、社員一人ひとりの成長と組織全体の信頼関係構築につながります。 人材育成の新たな視点として、ぜひ社内研修や日常的なコミュニケーションに取り入れてみてはいかがでしょうか。
-

2023.11.07
サーバントリーダーシップとは?概要や注目されている背景について紹介
チームづくり近年、リーダーとメンバーとの信頼関係を構築するための手法として、「サーバントリーダーシップ」に注目が集まっています。 メンバーの自主性をより促すためトップダウン型からの変革を考えた場合、サーバントリーダーシップの導入は大変有効です。 また、シェアドリーダシップとの関連で興味を持っているという方も多いのではないでしょうか。 今回は、サーバントリーダーシップの概要や従来の支配型リーダーシップとの違いを解説し、今注目されている背景をご紹介します。 サーバントリーダーシップの概要 「サーバントリーダーシップ」は、「奉仕の精神で部下に接し、導く」という考え方をもとにしたリーダーシップ理論です。 1970年、ベトナム戦争の泥沼化やウォーターゲート事件などを時代背景に、アメリカのロバート・K・グリーンリーフ氏がヘルマン・ヘッセの短編小説「東方巡礼」から着想を得て提唱しました。 「サーバント(servant)」という言葉には、召使いや奉仕する人という意味があり、サーバントリーダーシップは「奉仕型」のリーダーシップと言うことができます。 リーダーが部下に対する傾聴の姿勢を持ち、自主性を認めながらそれぞれの能力の最大化を図ることで、目的を達成するというスタイルが特徴と言えます。 そのため、組織において協力し合う関係が生まれやすい点がメリットです。 従来の支配型リーダーシップとの違い 従来の「支配型リーダーシップ」は、明確な上下関係と強い統率力に基づくリーダーシップで、リーダーがトップダウンで指示や命令を出し、それに部下が従うことで目標を達成してきました。 一方、サーバントリーダーシップでは、リーダーが部下の話をしっかり傾聴することで関係を築き、ともに協力し合いながら目標を達成します。 また、リーダーが部下に対して支援を行うことで信頼が得られる点もサーバントリーダーシップの特徴です。 サーバントリーダーシップの発揮によって、部下の強みや自主性を引き出し、積極的な行動へ導くことが可能です。 従来の支配型リーダーシップは恐怖心や義務感で部下を行動させるという点が大きな特徴ですが、サーバントリーダーシップでは部下との信頼関係を大事にすることで部下自身が考えて行動するようになります。 このように、サーバントリーダーシップは、これまでの支配型リーダーシップとは正反対の考え方と言えます。 注目されている背景とは? 経済成長が著しかった時代では、リーダーが強い意志や価値観を貫くことで部下を強力にけん引していくスタイルが主流でした。 しかし、現在は、不確実で予測が困難な「VUCA時代」に突入しており、ビジネス環境が大きく変化し、顧客ニーズも多様化しています。 このような時代の中で企業が成長していくためには、不測の事態に柔軟に対応できる組織づくりが欠かせません。 リーダーがすべてを管理して意思決定していく従来のスタイルでは対応が遅れてしまうため、メンバー一人ひとりが主体性を持った組織にしていく必要があります。 また、必ずしも一人のリーダーの意見が正しいとも言えないことから、さまざまな経験や知識を持った人材の活用が求められます。 そのため、サーバントリーダーシップによって、個性を発揮しながら行動できる人材を育成することが重要です。 まとめ サーバントリーダーシップは、「奉仕の精神で部下に接し、導く」という考え方をもとにした「奉仕型」のリーダーシップ理論です。 傾聴などを行って部下との信頼関係を築き、部下自身が考えて行動するように促すのが特徴で、リーダーが部下に命令や指示を出して統率する、従来の支配型リーダーシップとは大きく異なります。 不確実で先が読みにくいVUCA時代において、サーバントリーダーシップは企業の成長に不可欠な考え方だと言えます。 ぜひ、自社へのサーバントリーダーシップの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
私が変わると、チームが変わる
ワンネス経営®プログラムは、インナーブランディング強化というアプローチを通して、 お客様企業が求める成果を達成していくという「新しいチームビルディングのプログラム」です。 イメージが持ちづらい点があるかもしれませんが、どうぞお気軽にご質問、ご相談ください。