Column
2022.01.25
リーダー必読!「褒めて伸ばす」の落とし穴
チームづくり

「わたし、褒められて伸びるタイプなんです」
ってよく聞きますよね。
逆に聞きたいんですが、叱られて伸びるタイプっているんでしょうか?笑。
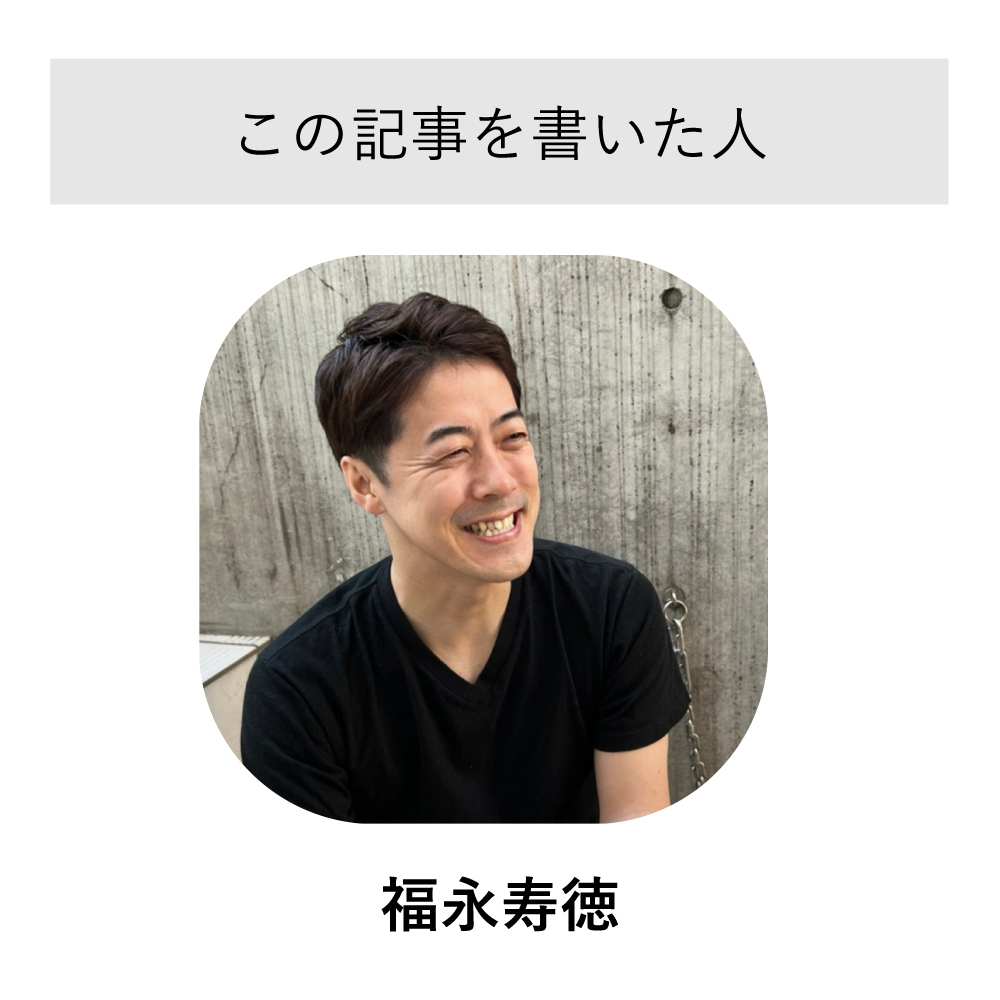
大学卒業後、ヘルスケア業界で1000名以上のトレーナーを育成。 セールス下手でも日本の隅々にまで展開することに成功。 好きで得意なことで役に立つと自分も周りも幸せだ。と確信する。 その後、独立起業。インナーブランディングの専門家として活動中。 趣味はトライアスロンだが走るのは嫌い。サウナとバスケ観戦が好き。 焼肉の部位はハラミ。フラップスプランの代表。
とりあえず、褒めて伸びるタイプですって先に言っておきたいのは、ミスっても叱らないで欲しいというただの防御策でしかないことをまずはご理解ください。
それでも、なお「褒めて伸ばす」
というのはなんとも甘美な響きであり、人材育成の理想郷な感じがします。
ところが「褒める」のが苦手という人も結構います。
褒めるのが苦手という人は大体どっちか。
- 自分の基準が高すぎて何をみても大したことないと思ってしまう
- 自分なんかに褒められても嬉しくないんじゃないかと思ってしまう
両方ボリューム調整せえよ。と思います。笑。
大したことないって言ってマウントとって何が都合がいいんでしょうか。
自分なんかに、って小さく見せて何が都合がいいんでしょうか。
褒めるというのは心の報酬です。
その効果をしっかり理解して褒めていきたいですね。
ただ!褒めるってのはなかなかの諸刃の剣です。
リーダーが知っておくべき「褒める」の落とし穴についてまとめました。
「褒める」と「承認する」の違い

早速ですがひとつ質問です。
「褒める」と「承認する」の違いって説明できますか??
「褒める」とは、
人のしたこと、行いを優れていると【評価】してそのことを言う。たたえること。
「承認する」とは、
そこにある事実を【認める】こと。
この違い。わかりますか?
「褒める」には【評価】が入っていて
「承認する」は【事実を認めて伝える】だけ
というのがポイントです。
人は誰からどんな風に褒められたい?

実は「褒める」というのは難易度が高いことなんです。
一歩間違えると、相手をねぎらって距離を縮めるつもりで言った言葉が、逆効果になってしまいます。
それは
人は【評価されたいと思う人から評価されたい】
という思いがあるからです。
尊敬している人とそうでもない人、どっちから褒められると嬉しいか。
もちろん、そうでもない人から褒められてもまあ、悪い気はしないんですが、やはり自分が尊敬していたり、自分のことをよく理解している人から褒められると嬉しいわけです。
同じ「褒める」にしても【誰が言うか】によって全然感じ方が変わってしまうのです。
どうですか?
あなたはスタッフから「褒められて嬉しい人」になれているでしょうか?
って聞かれるとドキッとしません?
褒める時は本音が大事
もう1つ褒めるときの落とし穴をご紹介します。
それは
本当にそう思っていないと嘘っぽくなる
ということです。
当たり前なんですけどね。
いわゆる「お世辞」ですね。
急に社員から
「社長、最近、吉沢亮に似てきましたね」
って半笑いで言われて
「えー!ほんとに?やっぱ最近ジム行き始めたからかなぁ」ってならんでしょ。
(いや、たまに本当にそう思う人がいるから経営者ってすごい。逆に。)
平均80点のテストで60点だった子に対して
「60点すごいじゃん!」
って言ってもなかなか届かない。
あ
まとめ
褒めるの落とし穴についてまとめてみました。
なんでも褒めればいいってもんじゃないんです。
- 褒められて嬉しい人になること
- 本音で伝えること
これを大事にしていきましょう。
今日はがんばったね。
じゃなくて、
今日もがんばったね。
です。
「は」と「も」で、かなり印象違います。
リーダーは言葉を磨いていきましょう。
生産性を向上させるコミュニケーション
チームリーダーと一般メンバーでは立場や経験の違いから、コミュニケーションがすれ違ってしまうことがあります。
すれ違いをなくすためには、伝える側と受け取る側の双方がそれぞれどのようなことを注意するべきなのか?ポイントを知りましょう。
円滑なコミュニケーションを行い生産性を向上させるヒントを公式LINEにて配信中です。今日からすぐに実践できるコミュニケーションのコツを知りたい方は下のボタンからLINEを追加し配信を受け取ってください!
事務局:スズキヒラク


この記事を書いた人
![]()
福永寿徳
大学卒業後、ヘルスケア業界で1000名以上のトレーナーを育成。 セールス下手でも日本の隅々にまで展開することに成功。 好きで得意なことで役に立つと自分も周りも幸せだ。と確信する。 その後、独立起業。インナーブランディングの専門家として活動中。 趣味はトライアスロンだが走るのは嫌い。サウナとバスケ観戦が好き。 焼肉の部位はハラミ。フラップスプランの代表。
関連記事
-

2022.07.26
チームビルディングの実践に役立つフレームワークとは?使える手法を詳しく解説
チームづくり「一人ひとりの能力が発揮できていない」 「チームがバラバラでまとまらない」 仕事の成果を上げるためには、メンバー一人ひとりが自分の力を発揮しながらチーム全体で目標達成に取り組む必要があります。しかし、理想的なチーム作りに悩む方も多いのではないでしょうか。 そのような課題を解決するためにも、ビジネスシーンにおいてチームの構築、すなわち「チームビルディング」が必要不可欠です。 チームビルディングとは、メンバーのスキルや能力、経験などを最大限に引き出して、まとまりのあるチーム作りに取り組むことを指します。 そこで本記事では、このようなチームビルディングに活用できる手法として、代表的な2つのフレームワークについて解説していきます。 チームビルディングに活用できるフレームワーク チームビルディングの手法には、代表的フレームワークとして「タックマンモデル」と「GRPIモデル」があり、これらを活用することでスムーズなチーム構築に役立ちます。 それぞれ詳しく見ていきましょう。 5つの発展段階を踏む「タックマンモデル」 「タックマンモデル」は、1965年に心理学者のブルース・W・タックマンが提唱した、チームビルディングの発達を表すモデルです。 理想の組織を作り上げるためにはさまざまな問題解決のプロセスを経る必要がありますが、これを以下の5段階に分けた考え方になります。 形成期(Forming)混乱期(Storming)統一期(Norming)機能期(Performing)散会期(Adjourning) このように段階に分類することで、チームが次の段階に移行するためにはどのようなチームビルディングが求められるのかが明確になります。 それぞれの段階について、以下で詳しく解説していきます。 形成期(Forming) 形成期(Forming)は、チームが結成されたばかりの最も初期の段階を指します。 この段階では、メンバーがお互いの性格や能力・考え方・価値観などが把握できていません。 そのため、緊張感やぎこちなさが生じがちです。 次の段階に移行するためには、メンバー同士がお互いのことを知り合うのはもちろん、チームとしての目標を確認し合う必要があります。 混乱期(Storming) チームでの活動を進めていくうちに、メンバー一人ひとりの仕事の進め方や考え方における違いが明確になります。 そこで意見の食い違いが発生し、軋轢や不満が生まれるようになる段階が混乱期(Storming)です。 この混乱期は、チームビルディングを行う中で必ず訪れるものとされています。 お互い納得いくまで話し合ったり、リーダーが業務量を調整することや一人ひとりのメンバーと向き合うことが重要になるでしょう。 統一期(Norming) 混乱期を乗り越え、メンバー全員が共通の目標や役割を持てるようになった段階が統一期(Norming)です。 メンバーがお互いのことを理解し、信頼関係が構築されるため、多少の意見の食い違いがあっても自然に解決される場面が多くなります。 ただし、間違った方向に統一されていては目標達成ができません。 この段階では、リーダーがしっかりビジョンを示し続けることに努める必要があるでしょう。 機能期(Performing) チームが組織として成熟し、メンバー個人の自立性が高くなる時期が機能期(Performing)です。 メンバーは自身の役割を正しく認識し、率先して行動できるようになります。 また、お互いをサポートし合いながらまとまって活動するため、次々と成果が出てきます。 チームとして最もパフォーマンスを発揮できる時期ですが、長続きさせるには、リーダーがメンバーに対してリフレッシュを促すといった工夫も必要になるでしょう。 散会期(Adjourning) 目的を達成できたり、時間の制約を受けたりしてチームが解散する時期が散会期(Adjourning)です。 メンバーはそれぞれ次の目標やプロジェクトに向けて動き出しますが、リーダーからポジティブな感想を伝えることで、より前向きに進んでいけるでしょう。 4つの要素を考える「GRPIモデル」 「GRPIモデル」は、組織開発コンサルタントのベックハード氏が提唱した、組織の健全性を考えるフレームワークです。 このモデルでは以下の4つの要素に着目し、健全に機能しているかを順番にチェックしていきます。 Goal(目標)Role(役割)Process(手順)Interaction(関係性) 4つの要素の頭文字を取って「GRPI(グリッピー)」と言われています。 目標達成に向けて、メンバーのあり方や手順など身近な部分にとらわれがちですが、この4つの要素を順番に確認していくことで本質に気づくことが可能です。 では、それぞれの要素を説明していきましょう。 Goal(目標) チームが目指すべき目標(ゴール)を明確にし、メンバー全員が合意できるように設定します。 無理な目標設定やリーダー一人で決めることは、メンバーのモチベーション低下につながりかねません。 必ず全員で話し合って、納得した上で決定するように心がけましょう。 Role(役割) 上記のGoal(目標)を達成させるため、タスクをピックアップしてメンバーの役割を決めていきます。 その際、スキル・知識・経験の観点で適切な役割をメンバーに割り振ることが重要です。 また、チーム全体のバランスを考慮した配置や不足分の補充の検討も必要になります。 Process(手順) メンバーの役割を決めた上で、目標達成するためにはどのような手順で進んでいくべきかを決定します。 ここでは、業務の手順や連携方法、意思決定フロー、評価基準などを明確にしなければなりません。 中間目標や細かな目標の設定によって、手順決定が容易になります。 Interaction(関係性) 目標達成には、チーム内での円滑なコミュニケーションが不可欠です。 目標・役割・手順を合意形成した上で、さらにメンバー間の関係性が重要になってきます。 日々のコミュニケーションは十分行われているか、お互いの信頼関係は築かれているか、といった点を確認する必要があるでしょう。 まとめ 今回は、チームビルディングの実践に役立つフレームワークを2つご紹介しました。 いずれの内容も、リーダーがチームビルディングにおいて心がけるべき事項ではないでしょうか。 また、チームが目標達成に向かうためには、メンバー全員の個の力が必要です。 能動的な状態で、最大限の力が発揮できるような環境作りが重要になります。 今回のフレームワークの内容を意識することで、チームをさらに強固なものにしていきましょう。 インナーブランディングを強化するワンネス経営®︎ インナーブランディングの強化を通じて、業績の向上に貢献するプログラムがワンネス経営®︎プログラムです。 コミュニケーションの質を高め、チームの生産性を向上させるために今すぐできるチームづくりのコツを公式LINE・Youtubeチャンネルで配信しています。 皆さんのチームビルディングのヒントにワンネス経営®︎をご活用ください! 事務局:スズキヒラク LINE友達追加はこちら!ワンネス経営®︎公式LINE 動画で学ぶことも可能です!Youtubeはこちら!ワンネス経営®︎公式Youtube
-

2023.03.20
次世代リーダー育成の3つの企業事例を紹介!
チームづくりこれからの企業において、ビジネス環境の急激な変化や後継者不足、意思決定・実行の必要性などの理由から、次世代の経営幹部の育成は必要不可欠だと言えます。 ただし、経営幹部の育成を実際に考える場合、どのように行えばいいのかわからない方も多いのではないでしょうか。 具体的に検討する際は、企業の事例を参考にすることで進めやすくなります。 今回の記事では、次世代リーダーの育成に積極的に取り組み、その成果が出ている企業の事例を3つ紹介します。 サントリーホールディングス株式会社の事例 サントリーは、グローバル企業として多くのM&Aを成功させています。 その中で、「One Suntory」の実現を目指し、次の時代を担う経営人材の発掘と育成に注力中です。 主な実施例としては、下記の3つが挙げられます。 リーダーシップ・コンピテンシー グループタレントレビュー会議 サントリー大学 それぞれ解説します。 リーダーシップ・コンピテンシー グローバル人材の必要性が加速する中、サントリーではグループ全体を先導するリーダーに向けて「リーダーシップ・コンピテンシー」を策定しました。 これに反映されているのが、創業精神に沿った「サントリーらしさ」です。 グローバルな環境においても、サントリーのカルチャーを大事にしながら活躍できる人材を育成するための取り組みの一つとなっています。 グループタレントレビュー会議 次世代リーダーを見つけるという点では、「グループタレントレビュー会議」を開催することで経営人材の発掘に取り組んでいます。 この会議によってグループ各社の人材情報を共有し、後継者育成計画や適切な人材配置に活用できるようになっているのが特徴です。 また、それに伴う育成プランも実行中です。 サントリー大学 サントリーは、グローバルに活躍できる人材を育てるため、2015年に「サントリー大学」を開校しました。 ここでは、“やってみなはれ”と“利益三分主義”というサントリーの創業精神への共感が進むような学習プログラムを展開しています。 また、米国のトップ大学と独自のプログラム開発を行い、ケースステディで学べる環境も提供中です。 「高い目標を立てて失敗も許容する」「アイデアを促進してそれをサポートする」といったサントリーならではの環境の中で、国境を越えた次世代リーダー候補を育成し、次々に輩出することに成功しています。 株式会社商船三井の事例 株式会社商船三井は、1884年に大阪商船として誕生して以来、130年余の歴史を有する世界最大級の総合海運企業です。 世界の資源を輸送する海運業を中心としたグローバルな事業展開を図っており、多彩な周辺事業の運営でも有名です。 主な実施例として次の3つが挙げられます。 MOL CHART One MOL グローバル経営塾 グローバル人材育成プログラム それぞれ解説します。 MOL CHART 株式会社商船三井グループは、3つの企業理念と長期ビジョンを掲げ、グループ全社員の行動指針として「MOL CHART」を制定しています。 「CHART」とは、「Challenge」「Honesty」「Accountability」「Reliability」「Teamwork」という5つの価値観の頭文字であり、社員が向かうべき方向として「海図」の意味も込められているのが特徴です。 「MOL CHART」では、「自律自責型の人材」を育成することを目指しており、そのため、「リーダーシップ」「コミュニケーション力」「ファイティングスピリット」「タフネス」という4つの素養を重視し、異文化や語学に関する教育も実施しています。 One MOL グローバル経営塾 「One MOL グローバル経営塾」は、2014年度から開始された社内スクールで、グローバルな環境でマネジメント力やビジョンを描けるスキルやマインドセットを学ぶことを目的としています。 対象者は、同社および海外現地法人の各部門から推薦された次世代を担う人材です。 期間は約1カ月半おきに5日程度ずつ日本で開催され、3回に分けて行われます。 プログラムは、イノベーティブな思考法やリーダーシップなどのフレームワークを学んだ後、小グループで「10年後の商船三井を創造する」というテーマに沿ってアクションラーニングを行い、最終日には経営陣に対し提言をプレゼンテーションするという内容です。 役員をメンターとするなど、受講生が一人ひとりの個性・ビジョンを発揮できるように工夫されたプログラムとなっています。 グローバル人材育成プログラム 経営塾への参加候補前の若手社員に向けては、35歳前後の国内グループの管理職層を対象にさまざまな人材育成プログラムを実施しています。 語学講座や海外赴任予定者への研修、経営リテラシーを学ぶ「経営スクール」などを通じて、グローバル人材としての育成を図ります。 日本電気株式会社(NEC)の事例 日本電気株式会社(NEC)は、1899年に米国の通信機器製造会社との合弁によって創業された、日本初の外資との合弁企業です。 コンピュータ技術とコミュニケーション技術の融合を意味する「C&C」という理念を通し、電話から始まり、通信、半導体、コンピュータへと事業を展開してきました。 日本電気株式会社では、グループ社員の普遍的な価値観として「NECグループバリュー」を作成し、これをベースに「人財哲学」を制定しています。 2016年からは、「人材哲学」を基にした「NEC 社会価値創造塾」を創設することで、次世代リーダー育成に取り組んでいます。 「NEC 社会価値創造塾」のプログラムは、下記の4つのモジュールが基本です。 共創学習 現地学習(ラーニング・ジャーニー) 内省学習 NEC変革プロジェクト 中でも特に大きな特徴となっているのが、「現地学習(ラーニング・ジャーニー)」です。 この学習には、フィリピンやザンビアへの訪問、また日本での介護実習や地方拠点への訪問を通して、自らの視点を広げる目的があります。 まとめ 今回は、次世代リーダー育成に役立つ主な3つの企業事例を取り上げて紹介しました。 企業によってリーダーの育成方法は異なりますが、いずれにおいても、「企業理念」を基にした取り組みになっていることがわかります。 次世代リーダーの育成を検討する場合、自社の企業理念をあらためて確認しておくことが重要です。 ぜひ、これらの事例を参考にして、次世代の経営幹部育成に取り組んでみてください。
-

2022.12.16
コンプライアンス研修を成功させる!3つのポイントを解説
チームづくり「コンプライアンス研修の実施が決まったけれど、成功させるためのコツを知りたい」という方も多いのではないでしょうか。 企業の不祥事防止や価値向上のため、コンプライアンス研修では法律や規律、コンプライアンスの重要性などを学びます。 コンプライアンス研修を行い、その効果を高めるにはポイントを押さえた実施が大切です。 今回は、コンプライアンス研修を実施する上でのポイントをご紹介します。 コンプライアンス研修を実施する際のポイントとは コンプライアンス研修を行う時の重要なポイントは下記の3つです。 階層別による実施 事例を使った実施 eラーニングやツールの活用 それぞれについて解説します。 階層別による実施 コンプライアンス研修を成功させる第一のポイントとして、社内の階層に分けた実施が挙げられます。 コンプライアンス研修にはテーマ別や業種・部門別、階層別といったタイプがありますが、おすすめは役割に合わせた階層別のものです。 例えば、新入社員と部長では行うべき業務や立場が全く異なります。 一般的に、役職が上がると責任範囲が広がるため、自身が直面するコンプライアンス問題も多くなります。 よって、受講する研修もその責任範囲に合った内容でなければいけません。 それぞれの責任範囲に合った知識を身につけるには、階層別に目的を設定して実施することが重要なのです。 下記に、3つの基本的な階層を取り上げます。 新入社員・若手社員 中堅社員 管理職 それぞれの階層の目的について説明していきます。 新入社員・若手社員 新入社員や若手社員の研修の目的は、コンプライアンスの基本的な知識を身につけることです。 加えて、社内規程や行動規範について学び、これらの重要性を理解する必要もあります。 コンプライアンス違反のリスクをしっかり認識した上で、研修が自社の価値を高めるといった意識も持てると良いです。 中堅社員 グループリーダーや主任といった中堅社員は、自身のコンプライアンス遵守と所属部署内のコンプライアンス違反のリスク回避などが研修目的になります。 そのため、コンプライアンスの必要性や重要性を理解するのはもちろん、コンプライアンス違反発生時の具体的な対処法を習得することが重要です。 また、この階層では業務に慣れてコンプライアンスに対する認識が甘くなるケースも多いため、改めて意識を高めるという目的もあります。 管理職 課長や部長などの管理職の研修目的は、的確なリスクコントロールやコンプライアンスに対応した組織づくりが行えるようになることです。 よって、研修では、世間一般の流れや自社についての理解を深め、コンプライアンスが会社経営に与える影響について自覚しなくてはいけません。 年齢層が高い場合も多いので、従来の認識や思い込みを捨てて新しい行動規範に適応する必要があります。 事例を使った実施 コンプライアンス研修では、具体的な事例を通した知識習得が効果的です。 有名な事例を取り上げることで受講者は興味関心を持ち、コンプライアンス違反の原因や起こった後の流れがスムーズに把握できます。 コンプライアンスの概要や難しい法令だけでは具体性に欠け、知識が習得しづらいものです。 特に、自社の業種の事例を取り上げることで身近なことと感じられるため、リスク抑止の高い効果があります。 初めに概要などを解説した上で、その内容に沿った事例を紹介することが大きなポイントになります。 eラーニングやツールの活用 このように、事例を通した研修には高い効果がありますが、集合研修という形式ではその場のみの学びになりがちです。 オンラインを使ったeラーニングやツールを活用すれば、各自で基本をあらかじめ学んだ上で研修に参加できたり、研修後に反復学習したりすることができます。 また、一人ひとりの理解度が図れるなどさまざまなメリットがあるため、導入を検討することも研修を成功させるポイントの一つと言えます。 まとめ コンプライアンス研修を成功させるコツとして、階層別の実施や事例を使った実施、eラーニング・ツールの活用が挙げられます。 これらのポイントを押さえることで効果の高い研修が実現するため、事前の確認がおすすめです。 ぜひ、今回の記事を参考にして、コンプライアンス研修を充実した内容にしていきましょう。
私が変わると、チームが変わる
ワンネス経営®プログラムは、インナーブランディング強化というアプローチを通して、 お客様企業が求める成果を達成していくという「新しいチームビルディングのプログラム」です。 イメージが持ちづらい点があるかもしれませんが、どうぞお気軽にご質問、ご相談ください。